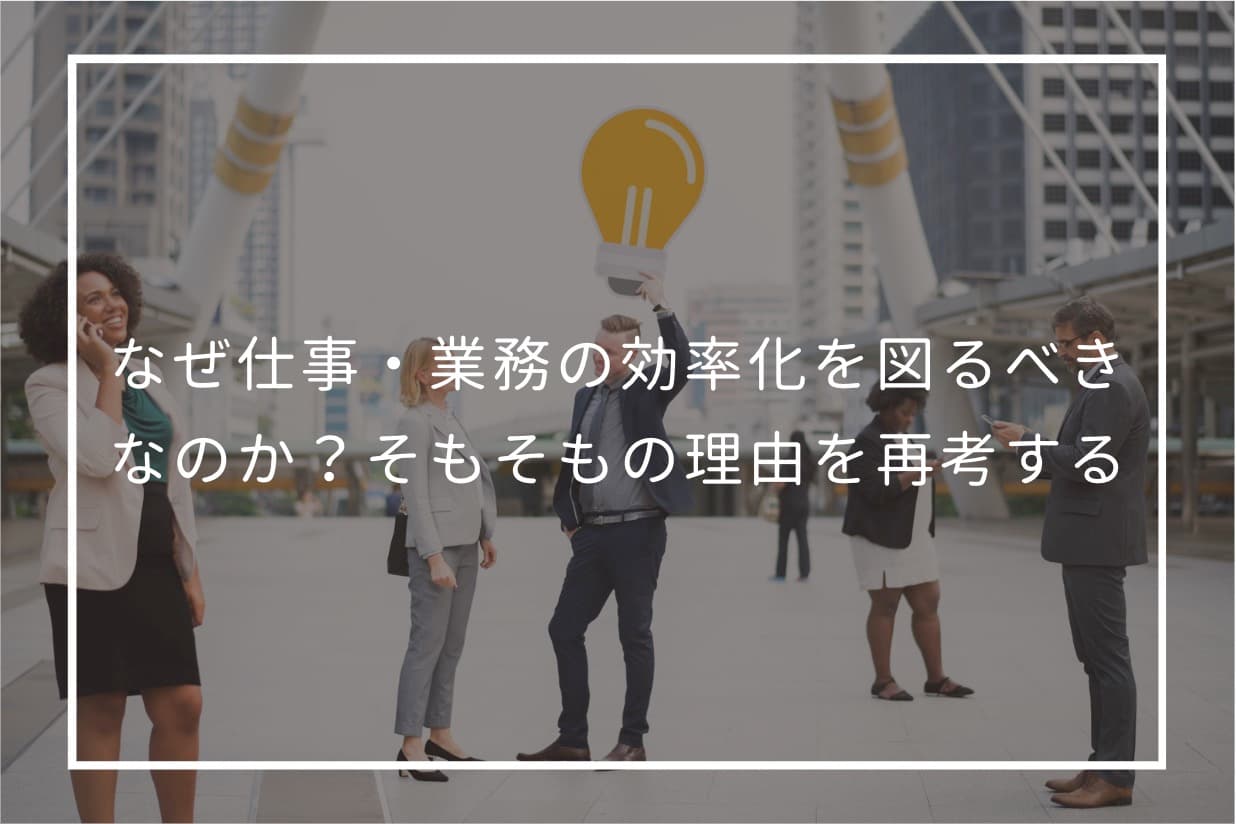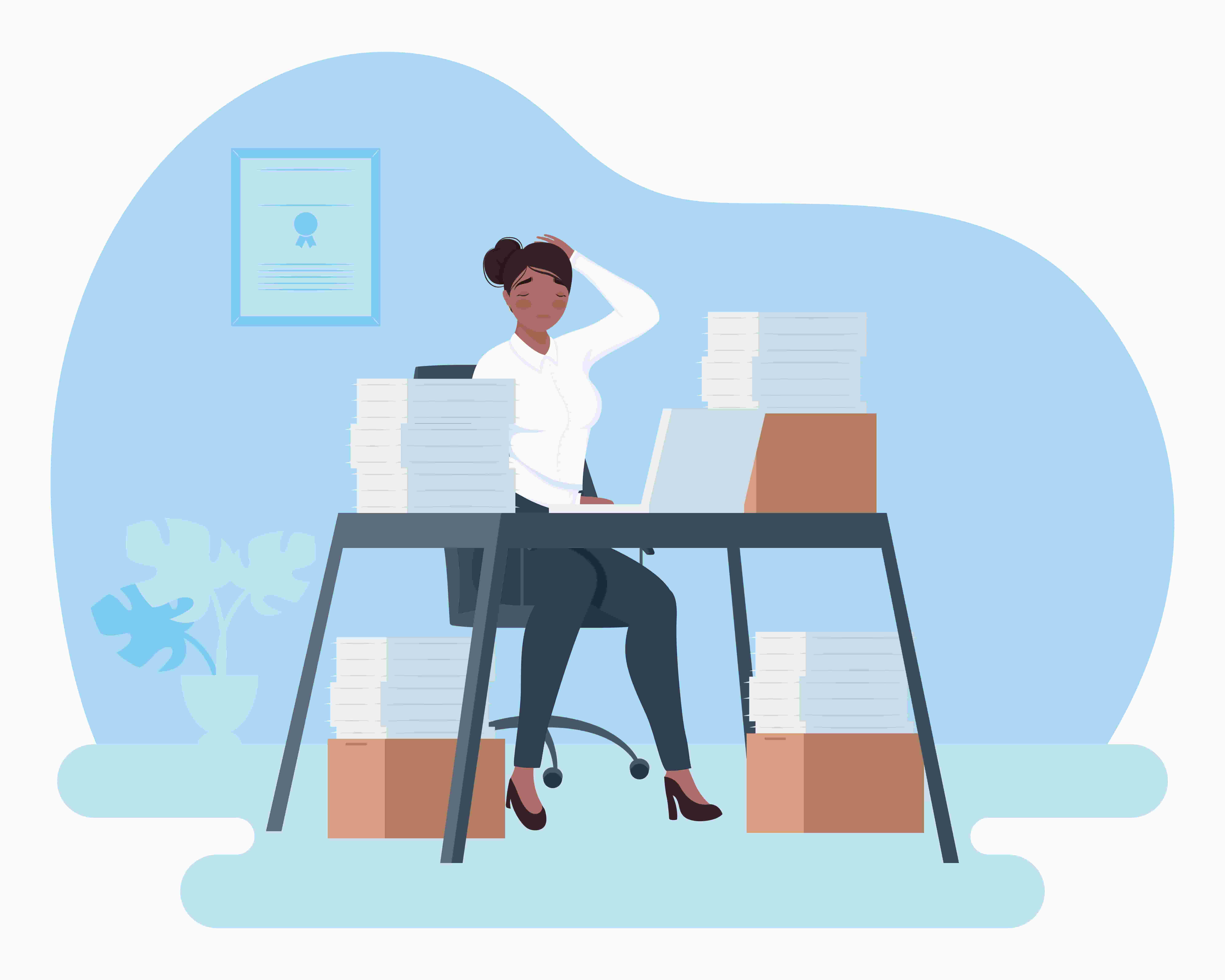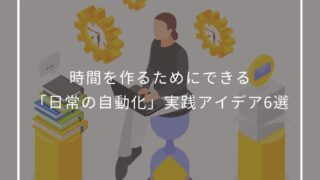けうzenです。
仕事の効率化や業務の効率化に悩み、求められることは増える一方なのに、評価は変わらない。効率化することに意味はあるのか、そもそも効率化を図るべき理由は何なのか、一度は疑問に思ったことがある方が多いのではないでしょうか。
降ってくるタスクは止まず、責任の量は増え、本来やりたいことの時間は確保できない。残業や持ち帰りが習慣化していて、効率化を試みても「モチベーションが続かない」「やった先に何が残るか実感できない」と感じている、そんな状態に心当たりがある方も多いはずです。
もしその悩みが、効率化に向き合う角度を少し変えるだけで、思ったよりシンプルに変えられるとしたら、どうでしょうか。
この記事では、そもそもなぜ私たちは効率化を強いられるのかという構造的な理由を整理し、いち個人としての幸福から効率化を捉え直す視点を解説していきます。
現状の仕事・業務の効率化のあり方に疑問を感じている方、強いられる効率化とは別に自分らしい生き方のための効率化の動機を持ちたい方は、ぜひ最後までお読みください。
それでは、どうぞ。
効率化が求められる原理的な理由
なぜ私たちは、これほどまで効率化を求められるのか。その背景には、私たちが生きる社会の構造的な理由があります。まずはその原理的な理由を、いち個人としての立場から見ていきます。
市場の競争原理
効率化が求められる最初の理由は、市場の競争原理です。
現代の市場では、顧客がより良い商品・サービスをより早くより安く求めます。これは、自分が客側になった時もそうだと思うので違和感はないと思います。そして、商品・サービスの提供者側は、顧客から自分たちが選ばれるために、より良い商品・サービスをより早くより安く提供する競争をしています。これが市場の基本的な仕組みです。
あなたが属する業界でも、おそらく同じような構造があるでしょう。ライバル会社がより魅力的な商品・サービスを打ち出せば、結果的に自分の会社にも影響が出ます。市場の競争が、最終的に「もっと早く」「もっと効率的に」という要求の形で、いち個人である自分にも反映されてしまうのです。
例えば、自分が3日かけて丁寧に作る資料と同じクオリティのものを、別の人が1日で仕上げることができる場合、どうしても比較されてしまうのが現実です。市場の競争原理がはたらく以上、効率化への一定のプレッシャーは避けにくいと言わざるを得ません。
限られたリソース
次に、人・時間・お金などのリソースが有限であることが、効率化が求められる理由としてあります。
一日24時間という制約は、地球にいる以上、現状は誰にも変えることができません。しかし、個人としてやるべきことは次々と増えていく傾向にあります。仕事の締切、家事、子育て、自分のスキルアップ、趣味の時間…すべてに十分な時間を割くのは、至難の業です。
同じように、自分の属する会社が使えるリソースにも限りがあります。理想を言えば、もっと余裕があれば良いですが、今あるリソースをなんとか有効活用する方法を考えざるを得ない、というのが多くの人が置かれている状況です。
企業としての利益最大化
企業は、営利企業である以上、利益を追求しなければ存続が危うくなります。同じ売上でもコストを下げられれば利益が増える。同じコストでより多くの売上を上げられれば、さらに成長できる。至極当然な摂理です。
その利益追求が、いち個人としての日常業務に効率化を求める理由です。
もちろん、会社の業績が良くなれば、それがボーナスや昇給として還元される可能性もあります。ただし、効率化の流れについていけないと、先も述べたように、会社が、引いてはいち個人としての自分が、立ちいかなくなる可能性が高まります。これが、多くの働く人が効率化と向き合うことになる根源的な背景です。
効率を求められる中で、やることが多すぎて困っている方は、以下の関連記事も参考にしてみてください。
「強いられる効率化」と別の意義を持ちたい
仕事・業務の効率化は私たち一人ひとりにとって避けられない課題かもしれません。ただ、この「外からの圧力」だけで効率化に取り組み続けるのは、正直なところしんどいものでもあります。
なので、ここでは「強いられる効率化」だけでなく、いち個人として別の場所に効率化の意義を持つことを提案します。どういうことか?順を追って説明していきます。
効率化を図ってもしんどい理由
効率化に成功すると、一時的には楽になったような気がします。ところが、残念ながらその状態は長く続かないことが多いです。
過去からの効率化の歴史を見ると、昭和、平成、令和と、時代が進むごとに技術は確実に進歩してきました。それなのに仕事はちっとも楽にならないのはなぜでしょうか。
それは、市場が相対的な競争だからです。どんなに効率化が進んでも、相手に勝っていないと意味がない。効率化に成功して優位に立っても、相手がまた更なる効率化を進めてくる。つまり、いたちごっこなのです。どんなに効率化が進んでも、更なる効率化が待ち受けているということです。
競争が前提の効率化は、どうしてもこのような「終わりのないレース」になります。
なぜ別の理由を持つことが重要なのか
なので、「会社から言われるから」「競争に負けないため」「評価されるため」、これらの理由だけで効率化を続けるのは、正直なところかなりしんどいものになってきています。
効率化が進むごとに、更なる効率化の難易度は高まり続けるからです。60点を70点にするより、90点を100点にする方が難しいのと同じ感覚です。
「外からの要求」だけで向き合う効率化は、自分がやりたくてやっているわけではなく、やらされている感覚が強くなってしまいます。そして、外からの要求は往々にして際限がないことが多いです。出来ないならもっと頑張れ、出来たらはい次もよろしく、というような感じです。
こんな状況に置かれて、思うような結果が出なかったとき、思うように評価されなかったとき、「何のために頑張っているんだろう」となるのは必至です。
だからこそ、外からの要求とは別に、あなた自身が「こういう理由で効率化したい」と思えるあなただけの意義を見つける必要があります。
会社と自分は一心同体ではない
ここで一つ、大切なことを確認しておきましょう。会社のために効率化することも必要かもしれませんが、会社と自分は別々の存在です。
会社と自分は両思いではないのです。自分が会社のために尽くしたいと思っていても、会社があなたに尽くしてくれるとは限りません。逆も同じです。会社と自分は一心同体ではないのです。
一方、自分が確実に一生付き合っていくのは「自分自身」です。どんな会社に勤めても、どんな職種に就いても、ずっとです。当たり前ですが、死ぬまで一緒です。
そう考えると、効率化のスキルや考え方も、会社のためだけでなく、あなた自身の人生をより豊かにするためのものとしても捉える方が、長期的には意味があるのではないでしょうか。
個人としての幸福から見る「効率化の意義」
これまで見てきたように、外からの要求だけで効率化に取り組むのには限界があります。では、どのような視点で効率化を捉え直せば良いのでしょうか。
ここからは、個人としての幸福という視点から、「幸福の三大栄養素」という考え方を中心に、効率化の意義を考えていきます。
幸福の三大栄養素とは
心理学の研究によると、人が幸福を感じるためには主に三つの要素が重要だとされています。それが「楽しさ」「満足感」「目的」です。
「タンパク質」「脂質」「炭水化物」のように、これら三つがバランス良く満たされている状態が幸福な状態であるという定義です。
効率化を通して、これら幸福に必要な要素を満たせれば、いち個人としての幸福な状態に辿り着きやすくなるというわけです。
幸福の定義は人それぞれですが、この捉え方が個人的に最も納得できているので、今回はこの捉え方を通して、効率化の個人的な意義を見出していきます。
先にお伝えすると、効率化はこの「幸福の三大栄養素」全てに貢献する可能性を秘めています。
「楽しさ」の視点:創造的な仕事への時間シフト
効率化によって単調な作業時間が短縮されると、より創造的な仕事に時間を使えるようになります。
例えば、データ入力や定型的な報告書作成のような作業を自動化できれば、その時間を企画立案や問題解決、新しいアイデアを考える時間に充てることができます。創造的な業務は、多くの人にとって単純作業よりも楽しく、やりがいを感じやすいものになりやすいです。
その意味で、効率化は「つまらない時間を減らして、楽しい時間を増やす」ための手段と見ることができます。
「満足感」の視点:「できるようになった」達成体験
効率化に取り組むプロセス自体が、「満足感」を得る機会になり得ます。
新しいツールを使えるようになったり、業務の手順を改善したり、時間短縮のコツを身につけたりするなど、「できなかったことができるようになる」「できることが増える」という前進・成長は、仕事に対する満足感を押し上げてくれます。
競争のための効率化では、他人との比較が中心になりがちですが、個人の成長に注目した効率化は、過去の自分との比較ができるため、他者依存しない満足感が得られやすいです。
「目的」の視点:仕事の自己選択
効率化に取り組む理由を自分で決めることは、仕事に対する「目的」に意識を向けることにつながります。
なぜ効率化するのか、その答えに自分なりに当たりをつけると、日々の業務が単なる作業ではなく、人生全体における意義のある活動として位置づけやすくなります。
例えば、「家族との時間を大切にしたいから」「新しいスキルを学ぶ時間を確保したいから」「将来の夢に向けた準備時間を作りたいから」など、自身の価値観や目標に基づいた理由を持てれば、効率化という行為に自分の意思で選択する動機になるでしょう。
また、どの業務をどのように効率化するかを自分で選択することも、仕事における自己選択感を高めます。
以上、幸福の三大栄養素に対する効率化の意義を見てきました。
強いられる効率化よりも、個人としての幸福に近い捉え方が広がったのではないでしょうか。
次節では、これらの考え方を具体的にどう実践に活かすか、具体例を交えて見ていきます。
効率との向き合い方【具体例】
では、個人としての幸福の視点を、実際にどのように効率化に活かせるでしょうか。
ここでは、楽しさ・満足感・目的それぞれにフォーカスした効率化の具体例をご紹介します。
【楽しさ】定型業務を自動化して、企画やアイデア出しの時間を確保
田中さんは、IT企業の法人営業担当で、毎月末、既存顧客20社への月次報告書作成に丸2日間を費やしていました。
各顧客のシステム利用状況データを管理システムから取り出し、表計算ソフトで数字をまとめ、定型フォーマットの報告書を作成する作業です。必要な業務ではありますが、同じパターンの繰り返しで、正直面白みを感じていませんでした。
そんな時、「この時間を新規顧客への提案企画に使えたらどんなにいいだろう」と思い立ち、効率化に着手しました。プログラミングができる同僚に相談して、顧客データを自動で取得・集計、プレゼン資料のテンプレートに自動で数字を入れ込む仕組みを作成。作業時間を2日から3時間に短縮しました。
その結果、
- 月末の1.5日を新規開拓のための業界研究と提案企画に活用
- 「この業界にはどんな訴求が刺さるだろう」と考える創造的な時間が増加
- 新規提案の成約率が向上し、顧客から「面白いアイデアですね」と言われる機会が増えた
田中さんにとって効率化は、「ルーティンワークを減らして、創造的な仕事を増やすための手段」となりました。会社の売上目標達成のためだけではなく、自分がより楽しく働くための選択として効率化に取り組んだのです。
【満足感】小さな工夫の積み重ねで残業時間半減
佐藤さんは、製造業の総務部で、毎日21時頃まで残業するのが当たり前な状況に、「自分は要領が悪いのかもしれない」と悩んでいました。
主な業務は社員の各種申請処理、会議室予約管理、備品発注、来客対応など多岐にわたります。一つひとつは小さな作業ですが、積み重なると膨大な時間になっていました。
大きく変えるのは難しいけれど、小さな改善なら毎日できるはずと考え、日々の業務を一つずつ見直すことにしました。
その結果、
- 「今週はメール作成が早くなった」など小さな成長の実感
- 残業時間が月45時間から25時間に減少
- 「昨日より今日、今日より明日」と少しずつ改良していく達成感
佐藤さんは効率化を「他の人に負けないため」ではなく、「昨日の自分を少しでも上回るため」の活動として捉えました。毎日の小さな改良に満足感を見出すことで、効率化そのものが前向きな習慣となりました。
【目的】副業準備のために業務効率化に取り組み
山田さんは、金融機関のシステム部所属で、将来的にフリーランスのWebサイト制作者として独立することを目標にしていました。
現在の業務は社内システムの運用・保守が中心で、最新の技術に触れる機会が少ないため、副業で新しい技術を学びたいと考えていました。しかし、日々のシステム監視、トラブル対応、定期メンテナンス業務で平日は22時頃まで、休日も緊急対応で呼び出されることが多く、学習時間が確保できずにいました。「独立を実現するために、まず本業を効率化しよう」という目的で、効率化に取り組みました。
その結果、
- 平日夜2時間×3日、休日4時間×2日で週14時間の学習時間を確保
- 最新のWebサイト制作技術を習得し、副業案件を受注開始
- 本業で身につけた効率化スキルが、フリーランス案件でも評価される
山田さんにとって効率化は、「会社の業績向上のため」だけではなく、「自分の人生設計を実現するための戦略的手段」となりました。明確な目的があることで、時には面倒な自動化作業を自己選択して取り組めたのです。
効率化の理由を、いち個人の幸福の視点から捉え直すことで、効率化との向き合い方を調整することができます。外からの要求に応えるだけでなく、あなた自身にとって意味のある効率化を見つけることが、持続可能で充実した働き方、引いては生き方につながります。
さらに具体的な効率化の考え方については、以下の関連記事をあわせてお読みください。
また、一個人としての幸福から効率化を捉え直すとき、無駄な時間を見つける足掛かりが欲しい方は、以下の関連記事もぜひご参考ください。
まとめ
今回は、昨今の効率化に疑問を感じている方に向けて、「なぜ効率化が求められるのか」という根本的な理由と、個人としての幸福の観点から効率化を捉え直す見方について解説しました。
- 私たちが効率化を強いられる根本要因には、市場の競争原理・有限なリソース・企業の利益追求という構造的背景がある。
- 「強いられる効率化」だけでは疲弊しやすく、幸福かどうかは疑問が残る。
- 個人としての幸福(楽しさ・満足感・目的)から効率化を捉え直すことは、より持続可能で前向きな動機を持つことにつながる。
- 「単調な業務を自動化して創造的な時間を増やす」「小さな工夫と成長に満足感を見る」「目的に沿って効率化を自己選択する」といった具体的手段がある。
効率化は「会社のために仕方なくやること」ではなく、自分の人生をいち個人として豊かにするための選択肢になり得ます。
外からの要求に従うだけの効率化は際限がなく、長期的には疲弊につながりますが、個人としての幸福のために効率化を活かす視点を見出せれば、効率化との向き合い方にも選択肢を持てます。
まずは「何のために効率化すると考えたら、良い未来を想像できるか?」を問い直すところから始めてみてください。それが、自分らしい効率化との向き合い方のヒントであり、動機となります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。