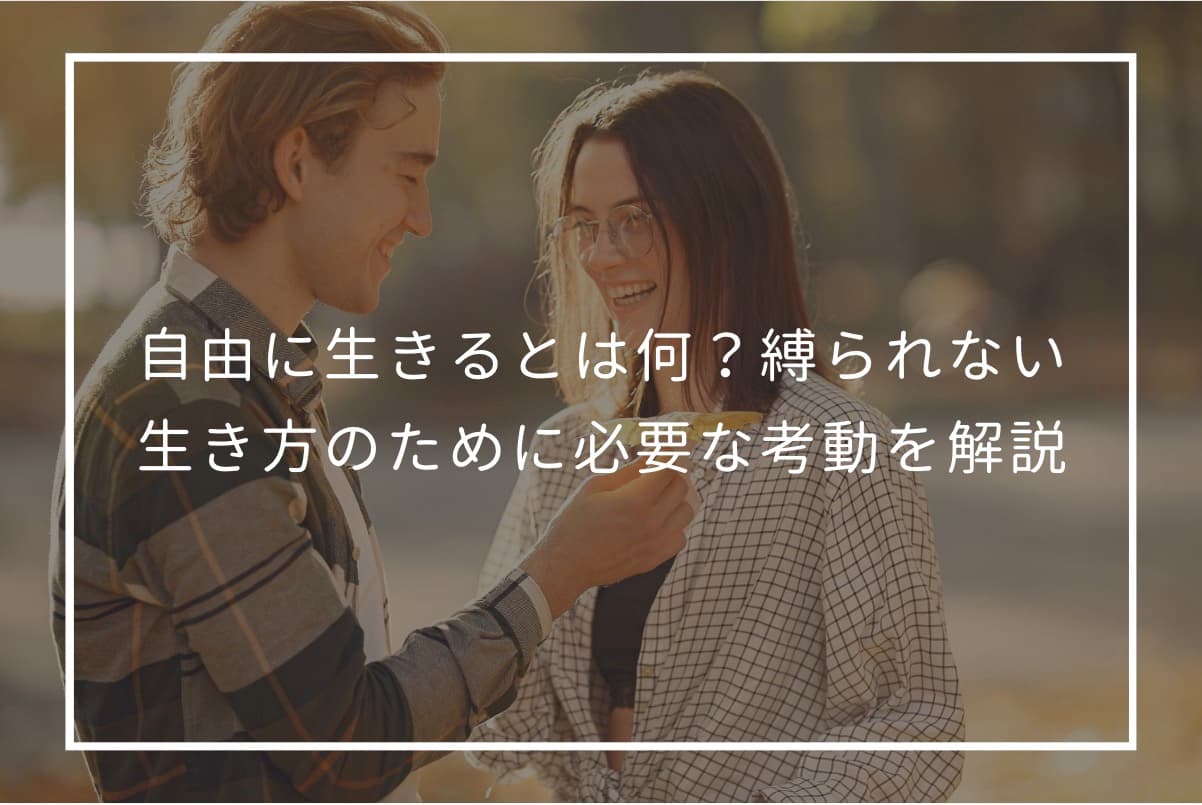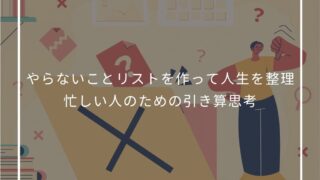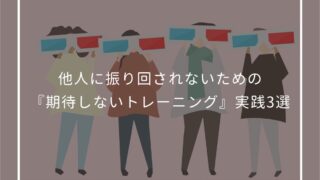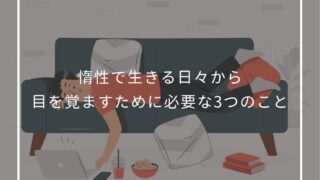けうzenです。
「もっと自由に生きたい」——誰もが一度は頭によぎったことのある考えかもしれません。
仕事や人間関係・社会常識に縛られていると今感じている方は、自分らしく生きたいと願いつつも、では「自分らしさ」とは一体何なのか?現実世界の中で具体的にどんな考動が自分の考える自由につながるのか?分からなくなっているのではないでしょうか。
自由に生きているように見える人を目の当たりにして、それをただ羨むしかできない自分が嫌になることもあるでしょう。しかし、他人に感じる自由は必ずしも自分の求めるものではなかったりします。ではどうすれば、自分が真に求める「自由」とは何かを知り、今を変える一歩目を踏み出せるのでしょうか。
この記事では、以下の点について解説していきます。
- 自由に生きるとは何なのか
- 私たちの自由を妨げる要因
- 偽物の自由の見分け方
- 自由を引き寄せるための具体的な考動
「自分だけの自由な生き方」を見つけ、一歩目を踏み出したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
それでは、どうぞ。
自由に生きるとは何か?
そもそも「自由に生きる」とはいったいどういう状態なのか?何となくイメージはあるけど、言葉にはできない、という方も多いのではないでしょうか。ということでまずは、「自由に生きる」とは何か、について見ていきます。
「自由に生きる」のよくある誤解
「自由に生きる」と聞くと、自分勝手に過ごすイメージや責任を取らないことと結びつくことがあります。しかし本当の自由は他者への無関心や無責任さではありません。むしろ自由とは、自分の価値観で選択し、その結果に対して自分で責任を取れる状態です。
たとえば「残業を断って趣味の時間を確保する」ことは一見自己中心的に見えるかもしれませんが、「業務時間内に必要な作業を終わらせている」のであれば、自身の責任に基づいた合理的な判断であり、これこそ主体的な「自由な選択」です。
「自由に生きる」の本質
自由の本質を一言で言えば、「自分の価値観に基づいて選択できる状態」です。社会や他人の期待ではなく、あなた自身の基準で物事を決められること。重要なのは「他人と違う生き方=自由」ではなく、「あなたが納得できる基準で選べているかどうか」です。
自由の3つの側面
とはいえ、一口に「自由」と言っても、その中身は複雑です。自由は、大きく分けて3つの側面から成り立っています。
1つずつ詳しく見ていきます。
精神的自由:他人の目や評価に左右されず、自分の価値観で選択できる
他人の期待や社会的ルールに振り回されず、自分の考えや意思で物事を決められる状態を指します。
- 例1:会議で自分の意見を言える、同僚や上司の反応に怯えずに主張できる
- 例2:友人や家族の意見に左右されず、自分のライフスタイルや趣味を選ぶ
精神的自由を得るためには、自分の価値観を明確にすることが重要です。「こうあるべき」という社会的ルールや他人の期待ではなく、自分にとって納得できる基準を決めておくことが、自由な選択につながります。
時間的自由:働く時間・休む時間・自分時間を自分でコントロールできる
一日の過ごし方や仕事・休息のタイミングを自分で決められる状態です。
- 例1:仕事の時間帯を自分で調整できる
- 例2:趣味や学習のためのまとまった時間を確保できる
時間的自由は精神的自由とも深く関わっています。例えば「残業続きで趣味の時間が取れない」と感じる場合、精神的には自由を感じても、時間的制約によって行動が制限されている状態です。自由を実感するには、まず自分の時間を意図的にコントロールする工夫が必要です。
経済的自由:選択肢を持って、自分の望むライフスタイルを実現できる
生活や選択を支える収入・資産があり、制約少なく自分の行動を選べる状態を指します。
- 例1:収入が安定しており、やりたいことに挑戦できる
- 例2:生活費や学び、旅行などの選択肢に制約が少ない
ただし、注意が必要なのは「お金=自由」ではない点です。いくら高収入でも、自分の価値観や時間を犠牲にしている場合は、苦しいです。収入が多くても精神衛生を壊す仕事はできません。お金があっても、使う時間がなければ意味がありません。経済的自由は、自分が本当に大切にしたいモノ・コトを理解し、それに必要な量を把握することが第一歩です。
精神的自由・時間的自由・経済的自由は互いに関連しています。
- 精神的自由がなければ、経済的・時間的に自由でも「自由選択」できない
- 経済的自由がなければ、精神的自由や時間的自由を十分に活かせない
- 時間的自由がなければ、経済的自由を行使できない
3つに分けて考えると、自由のために具体的に何ができそうか、少し掴めてきたのではないでしょうか。自由とは単なる「好き勝手にできる状態」ではなく、精神・時間・経済のバランスが整った状態でこそ実感できるものです。自分に今どの側面が不足しているか考えることで、「自由に生きる」ことの輪郭が見えてきます。
出発点としての「不自由」
「自由」の構成要素が見えてきたところで、次は具体的な考動の取っ掛かりを見つけていきます。
自由に生きるとは何か、興味を持ってここまで読み進めてきたということは、あなたは今現在の状況に何か不自由を感じているのでは無いでしょうか。時間が足りない、経済的に余裕がない、意見が言えない、尊重されてない。具体的な不自由は、あなたの中にある「譲れない価値観」に触れていることが多いです。
ここで重要なのは、不自由を漠然としたイメージのままにしないこと。不自由を言語化してみてください。
なぜ不自由の言語化が必要か。それは、あなたの感じている不自由は、自由に向かう考動の出発点となるからです。不自由を特定すると、次の考動が明確になります。不自由を解消するのです。あなたの抱える不自由を1つ解消できれば、1つ自由に近づきます。
たとえば「時間がない」が不自由の核心なら、まずは何に時間を多く取られているのか、24時間表に書いてみる。重要なのは、今感じている不自由を言葉にして、自由に向かう考動の起点を見つけることです。
なぜ私たちは自由に生きられないのか
では、なぜ私たちは自由に生きることが難しいのでしょうか。それは、現実世界に存在する要因が制約として私たちの考動を制限するからです。
思い描く生き方を実現できない要因を、3つに分けて解説していきます。
1. 心理的要因 — 失敗への恐れ/他人に嫌われたくない気持ち
- 失敗の恐れ:
自由にはある程度の不確実性が付き物です。未知の選択は「失敗するかもしれない」という不安を伴い、結果として現状維持(安全策)を選びがちになります。 例:独立してみたいが「収入が途切れたらどうしよう」と考え踏み出せない。 - 社会的承認欲求:
他人の評価を気にするあまり、自分の本心を抑えて周囲に合わせると、精神的自由は得られません。評価を失うことを恐れて重要な選択を人任せにしてしまう。 - 自己イメージの固定:
「私は○○な人間だ」という無意識の自分像(例:堅実な人、勤勉な人)に縛られ、本当に望む選択ができないケース。自分像を変えること自体に抵抗が働きます。
2. 現実的要因 — 経済不安/スキル不足/ライフステージの制約
- 経済的リスク:
生活費、家族の扶養、ローンなどの現実的な負担は、リスクを取る余地を狭めます。経済的基盤が不安定だと、「自由な選択」を行う余裕がありません。 - スキル・ネットワークの不足:
自由な働き方や転身には、実務スキルや人脈が必要になることが多いです。それらが不足していると選択肢が限定されます。 - 家庭やケアの制約:
子育てや介護などライフステージ上の制約は、時間的・地理的な自由を制限します。これらは軽視できない現実的ハードルです。
3. 社会的要因 — 「安定重視」の教育・文化・制度
- 教育や風土の影響:
多くの社会では「良い学校→良い会社→安定した人生」というモデルが長く尊ばれてきました。こうした価値観は選択肢の枠組みを狭め、「自由は危険」という先入観を生みます。 - 制度的な縛り:
雇用形態、社会保障、税制などの制度構造が、転職や独立を難しくしている場合があります。制度面の制約が行動を抑制することも少なくありません。
自由の虚実の判別ができていない — 「追いかける自由」が偽物であること
多くの人が「自由」と聞いて思い描くイメージ(高収入・ノマド・有名人のライフスタイルなど)は、実は他者やメディアが作った単なるコンセプトであることが少なくありません。消費者である私たちの興味を惹くために作り上げたマスコットのようなものです。こうした〈見かけ上の自由〉を追い続けるのは、むしろ自分の求める自由から遠ざかることにつながるかもしれません。
本当に自由に生きてる人は、その生き方を他人に見せびらかすことはありません。見せる必要がないからです。そして、一方的にこれが正解だと決めつけることもないです。自由は人によって異なるので、自分の考えが他者にもそのまま当てはまる保証はないからです。仮にアドバイスを求められた時でも、その回答はあくまで提案であることが多いでしょう。
自由の虚実を見極める簡易チェック
次の問いに「Yes/No」で答えてみてください。
- これを実現したい理由は自分の内側から来ているか?(外からの期待・流行ではないか)
- 実現後に失うものは何か、それを許容できるか?
- その選択をしても自分が日常で納得感を得られそうか?
- 「実現した自分」を具体的にイメージできるか?(感情・日常の描写まで)
- その自由を維持するための現実的な手段(収入・人間関係・健康)は見えているか?
「No」が3つ以上なら、その自由像は自分の深い価値観に根ざしていない偽物の可能性が高いです。
自由に生きるための考え方案(マインドセット)
自分の自由に向かっていくために、まず「考え方」を新しく取り入れることを提案します。魚を釣るためにいきなり釣り糸を垂らすよりも、場所、時間帯、エサ、道具の使い方など、知識をある程度つけた方が釣りやすいからです。
ここでは、すぐに実践できるマインドセットをお伝えし、具体的な考動を決めていくための土台を提供します。
主体性を持つ — 「正解は自分が決める」
自由に生きるための第一歩は、主体性を持つことです。主体性とは、他人や社会が用意した選択肢だけに従うのではなく、自分の基準で考動を決める姿勢をいいます。
日常の小さな選択から、自分の基準を意識する練習を始めましょう。たとえば、今週の外食に「本当に自分が食べたいもの」を決めることです。そして、その選択をした理由を言葉にしてみてください。
他には、普段よく迷う場面に対して「自分なりのルール」を作ると良いでしょう。例えば「家族の意向より、自分の体調を優先する」といった短いルールを設けて、その通りに動いてみましょう。もちろん「家族を大切にしたい」という主体性も自分の中に存在するでしょう。その場合は、「自分の体調」と「家族」のバランスを自分の意思で調整していけばいいのです。自分の意思を尊重する習慣が身につきます。
他人の評価より「自分にとっての納得感」を優先する
私たちは無意識のうちに、他人の評価や承認を基準にしてしまうことがあります。しかし、思い出してください。自由の本質は、「自分の価値観に基づいて選択できる状態」でした。本当の自由を手に入れるには、外向き(承認)ではなく内向き(納得)の判断を優先することが重要です。他人の評価に左右される状態は自由とは言えないでしょう。
この見極めには「承認欲求を可視化する」方法が効きます。たとえば、ある行動を取るときに「それで得たいものは何か?」を3つ書き出してみます。「認められたい」が一番に来る場合、その行動は承認欲求に依存している可能性があります。もちろん承認欲求を完全に否定する必要はありませんが、自分の納得感を満たす行動を増やすことが、他人の評価と独立した自由度を高めます。
SNS発信を例にすると、承認を求めて発信するのではなく、「自分の思考を整理するため」「誰かの役に立つ情報を届けるため」という内から来る目的を意識することが、より自分軸に沿った行動につながります。
自分の今の価値観を一度疑ってみる
主体性の根源となる自分の価値観は、私たちが今まで生きてきて見たもの・聞いたもの・触れたもの・感じたことから形成されています。この価値観には、自分の意思で選んだものではなく、親や社会から植え付けられたものも含まれています。つまり「主体的に選んだ価値観を追いかけて苦しんでいたら、実は他人に刷り込まれた価値観をなぞっているだけだった、どうりで苦しいはずだ」となることもあり得るのです。
この「他人に刷り込まれた価値観」の確認には、「もしもその価値観がなかったら、自分はどう生きるか」をイメージする方法があります。たとえば「安定した仕事を持つべき」という価値観がなければ、もっと挑戦していたかもしれないと感じるなら、それは刷り込まれたの価値観の可能性があります。
この作業はおそらくお伝えする考動案の中で最も難しいです。今まで自分が十数年、もしかすると数十年、正しいと信じてきた価値観を疑って見ることになるからです。不要と見改めた価値観を薄め、残したいものを自分の価値観として濃くしていきます。例えば「安定は大事だが、年に1回は挑戦する」というように、自分の意思を組み込んでいくことが大切です。
不安・恐れへの向き合い方 — リスクを分解して管理する
自由を目指す過程では、不安や恐れがつきものです。しかし、不安や恐れを理由に行動を止めてしまうと、リスク0のものしかできなくなります。この世の中でリスク0のものは万に一つもないでしょう。リスクなくしてリターンはないのです。重要なのはリスクを漠然と恐れるのではなく、分解して管理することです。
まず「最悪のシナリオ」を具体化します。たとえば転職であれば、最悪は「収入が一時的に減る」「業務が自分に合わない」かもしれません。不安が具体化できたなら、それを回避・軽減する策を考えます(セーフティな生活資金を概算する、具体的な業務内容調査を深める、など)。さらに、最悪が起きた場合のリカバーも準備することも不可能ではありません。不安なことは言語化できると、事前に対処する方法がいくつかはあるものです。
また、大きな決断をする前に、小さな実験(プロトタイプ)を試すのも有効です。副業を始める、短期移住を体験するなど、リスクを低くした実践を重ねることで、実際に動かないと分からなかったことが分かり、不安や恐れが軽減されていくこともあります。
継続的に自分の自由をアップデートする
環境や価値観は時間とともに変わります。そのため、定期的に「今自分があろうとしてる自由は、今の自分の考えに合っているか」をチェックして、アップデートすることが重要です。
1〜3年ほどの比較的長いスパンごとに、自分の自由に対する満足度や維持コストを振り返ってみましょう。今まで大事だと思っていたものを外しても問題ありません。今の自分の考えに沿うよう調整して、小さな改良を積み重ねていきましょう。定期的な見直しで、これからの自分のために、今の自分が思う最良の自由を更新していけます。
自由を実現するための具体的行動案
最後に、精神的・時間的・経済的自由を現実化するための具体的行動を紹介していきます。日常生活に組み込む方法案も併せて提示しているので、具体的な行動に迷ったときに参考にしてもらえればと思います。
精神的自由を高める行動
- 習慣的な内省:1日1分、自分の感情や選択に向き合う時間を持つ。
方法案:日記やメモに「今日自分は何を感じたか」「どの判断が自分軸だったか」を書く。 - 情報の取捨選択:SNSやニュースなど、不要な情報は減らす。
方法案:SNS通知をオフにする。情報源を3つ以内に絞る。 - 境界線を引く練習:他人の期待に振り回されないためのルールづくり。
方法案:「夜9時以降は仕事メールを開かない」「週末、親族の誘いを断る選択肢を持つ」など。
時間的自由をつくる行動
- 優先順位の明確化:重要でないタスクは削減。
方法案:1日のタスクを「絶対やる」「できればやる」に分け、絶対やることだけを最初に実行。 - スケジュール可視化:時間を見える化して、隙間時間を意識的に確保。
方法案:Googleカレンダーや手帳で30分単位で予定を管理し、自由時間を先取りブロック。 - ルーティン化:日常タスクをルーティン化し、意思決定を減らす。
方法案:朝の身支度・メールチェック・運動など、固定時間でルーティン化。
経済的自由を得る行動
- 収入源の多様化:1つの収入に依存せず、複数ルートを確保。
方法案:副業や投資で補助的収入を得る。複数のクライアントを持つ。 - 支出の最適化:必要なもの・不要なものを明確化、浪費を減らす。
方法案:固定費の見直し、サブスクの整理、家計簿アプリの導入。 - 資産形成の習慣化:長期的視点で貯蓄・投資を組み込む。
方法案:給与の一定%を自動で貯蓄、投資に積立。
行動を継続するためのコツ
- 小さな実験:いきなり全てを変えず、1つずつ試す。成功体験を積むことが継続の鍵。
方法案:食事・睡眠・運動のうち、まずは睡眠だけ1つ新しいことを始める。 - 振り返りの習慣:週1回、自分の自由度が上がったかチェック。
方法案:タスク消化率、気分、収支状況を可視化する。 - サポート環境の構築:自分の自由を尊重してくれる人やツールを活用。
方法案:仲間との定例会、アプリで行動記録やリマインド。
持続的な自由のための仕組みづくり
- 自動化とアウトソーシング:繰り返し作業はツールや外注で効率化。
方法案:家事や事務作業の一部を自動化、定期的に手順を見直す。 - 意思決定の簡略化:選択肢を絞ることで、自由時間と精神的余裕を確保。
方法案:服装や食事のルール化、ルーティンタスクをテンプレート化。 - 自由の定期評価:年1〜2回、精神・時間・経済の自由度を振り返り、調整。
方法案:自由度スコアを5段階で自己評価し、改良点を言語化。
まとめ
今回は、「もっと自由に生きたい」と感じている方に向けて、自由とは何か?その本質と、そのために必要な考動について解説しました。
- 自由とは、他人や社会の基準ではなく、自分の価値観で選択できる状態。
- 自由の3側面:精神的自由・時間的自由・経済的自由には相互作用があり、バランスが大切。
- 現状の不自由を特定することが、自由に近づくための起点となる。
- 自由を妨げる要因:心理的・現実的・社会的な制約を認識し、対策を取る必要あり。
- 他人やメディアが作った「自由」に惑わされず、自分の価値観に沿った選択をする。
- 自由のためのマインドセット:主体性を持ち、納得感を優先し、価値観を疑い、不安と向き合う。
自由とは、好き勝手にすることではなく、「自分の価値観に基づいて選び、その結果に責任を持てる状態」です。
まずは今日、あなたが感じている不自由を一つ言語化して、その解消に向けて小さな一歩を踏み出してみてください。それが、あなたのスタートラインです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。