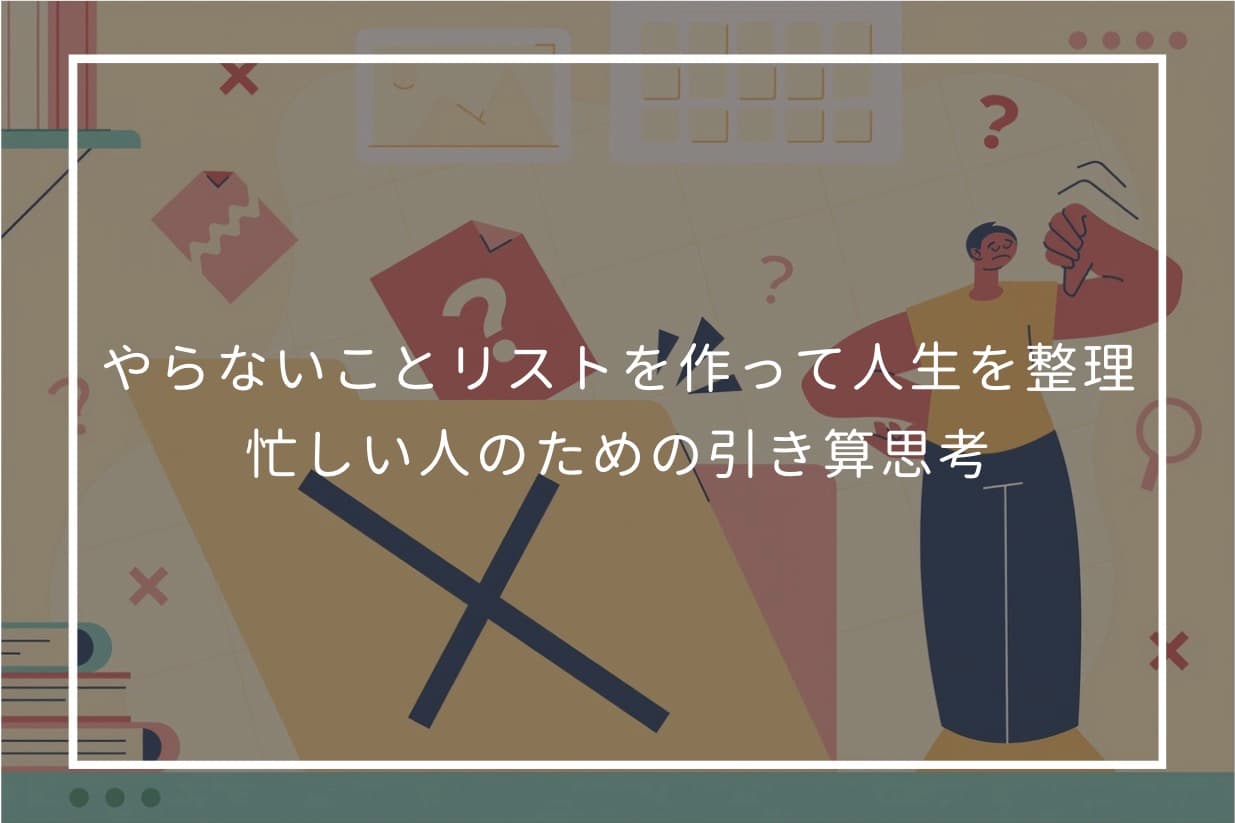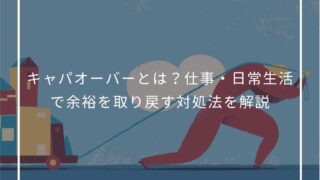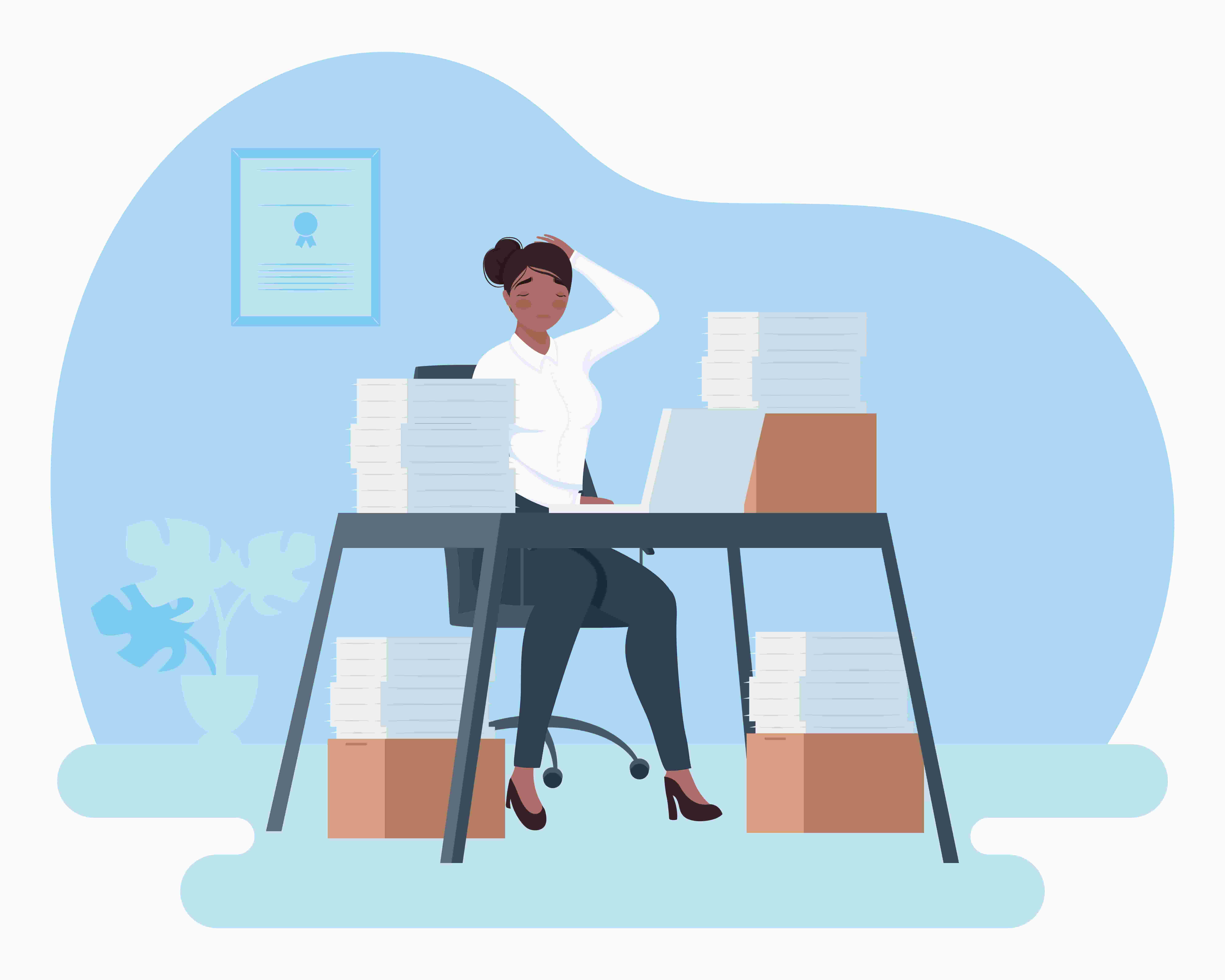けうzenです。
「今日も時間が足りない」「やることばかりで疲れた」—— そんな毎日を送っていませんか?
現代人の多くが抱えるこの悩み。実は、解決のカギは「何をやるか」ではなく「何をやらないか」を決めることにあります。
ToDoリストが「やること」を増やし続ける足し算の発想だとすれば、「やらないことリスト」は不要なものを排除する引き算の発想。この引き算こそが、情報過多で選択肢に溢れた現代を生きる私たちに必要な時間管理です。
投資家のウォーレン・バフェット氏が「成功の秘訣は、ほとんどすべてのことにノーと言うことだ」と述べているように、多くの成功者が実践しているのも、この「やらないこと」を明確にする手法です。
ということで今回は、やらないことリストの科学的根拠に基づく効果から、具体的な作成手順、実践のコツまでを詳しく解説していきます。記事後半では、やらないことリスト具体例50選もご紹介。
時間に追われる毎日から抜け出して、本当に大切なことに集中できる日々を手に入れたい方は、ぜひ最後までお読みください。
それでは、どうぞ!
やらないことリストとは?時間管理の新常識
やらないことリストとは、日常生活や仕事において「意識的にやらない」と決めた行動や習慣を書き出したリストのことです。一見すると消極的に思えるかもしれませんが、むしろその逆で、実は非常に効果的な時間管理のアイデアだったりします。しかもシンプル。
やらないことリストの目的
やらないことリストの最大の目的は、限られた時間とエネルギーを本当に重要なことに集中させることです。私たちの一日は24時間しかありません。何かを選ぶということは、必然的に何かを諦めるということでもあります。やらないことリストは、この「諦める」部分を意識的に選択するためのツールです。
ToDoリストとの決定的な違い
多くの人が馴染みのあるToDoリストとは、根本的な違いがあります。
ToDoリストは「やるべきこと」を追加していくリストです。一方、やらないことリストは「やらないこと」を明確にして、選択肢を絞り込むリストです。ToDoリストが「足し算」の発想なら、やらないことリストは「引き算」の発想になります。
この引き算の発想こそが、今の私たちに必要な考え方です。現代は情報過多の時代、私たちは常に様々な情報に晒されています。新しいタスクや誘惑が増え続けている今、やらなくていいことを決める価値が比例して高まっています。やらないことリストが明確にあることで、迷いなく、自分が大事と思える対象に時間を使えるのです。
日常がすでにキャパオーバー気味な方は、以下の記事も一読いただければと思います。
科学的根拠に基づく効果
心理学者のバリー・シュワルツは著書「選択のパラドックス(原著:The Paradox of Choice: Why More Is Less)」では、選択肢が多すぎることによる「選択疲れ」について言及しています。人間の意思決定能力には限界があり、日々無数の選択を迫られることで判断力が低下してしまうのです。
やらないことリストは、この選択疲れを軽減する効果があります。あらかじめ「やらない」と決めておくと、その都度悩む必要がなくなります。
また、複数の制約の存在が、かえって創造性を向上させることを示唆する研究があります。やらないことリストによって行動に制約を設けることは、残された選択肢の中でより創造的で効果的な解決策を見つけることにつながると考えられているのです。
制約が創造性の向上につながった身近な例として、日本の軽自動車があります。軽自動車は全長3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下、排気量660cc以下という厳しい制約があります。しかし、この制約があったからこそ、メーカーは限られたスペースを最大限活用する工夫を考え抜き、結果として普通車よりも室内が広い車種や、驚くほど燃費の良い車、取り回しの良さを活かした利便性の高い車を生み出してきました。制約という「やらないこと」が明確だったからこそ、創造的なイノベーションが生まれたといえる良い例です。
やらないことリストがもたらす5つの効果
やらないことリストを実践することで、あなたの人生にはどのような変化が起こるのでしょうか。ここでは、やらないことリストの効果を5つに分けて解説していきます。
時間の余裕が生まれる
やらないことリストの最も直接的な効果は、時間の創出です。無駄な会議への参加をやめる、意味のない飲み会を断る、SNSの無目的なスクロールをやめるなど、「やらない」と決めたことで空いた時間は、あなたの本当の目標や価値観に沿った活動に充てることができます。
例えば、「毎日1時間のテレビのだら見」をやめると、年間365時間(約15日分)の時間が生まれます。この時間を読書、スキルアップ、家族との時間、運動など、ありたい自分のための時間に充てれば、人生全体で見たときの充実度は少しずつ上向いていくでしょう。
抱えるストレスを減らせる
現代人のストレスの多くは、「やらなければならない」という義務感、そして「断れない」という罪悪感から生まれています。やらないことリストは、この精神的な重荷を軽減する効果を見込めます。
やらないことリストは、人生において自分が重要でないとした対象を諦める決心を示したものです。義務感や罪悪感、周囲の圧力に流されることもあるかもしれません。しかし(これが私の選択した生き方だ)と確信を持っていえる芯があるなら、流されることなく、判断できるようになります。
心理学の視点に立つと、人はコントロール感を持つことがストレス軽減に大きく寄与することが知られています。やらないことリストは、まさに自分の人生をコントロールする実感を与えてくれるツールとなります。
意思決定疲れが軽減される
1日に数万回もの決断を下していると言われる現代人にとって、意思決定疲れは身近な問題です。朝起きてから夜寝るまで、「何を着るか」「何を食べるか」「どの仕事から取り組むか」など、無数の選択に直面しています。
やらないことリストは、これらの選択の多くを事前に排除できます。結果として、重要な判断に集中できるようになり、判断の質が向上します。
Appleのスティーブ・ジョブズが毎日同じような服装をしていたのも、服装選びという意思決定を排除して、より重要な判断にエネルギーを集中するためだったと言われています。
価値観と人生の方向性が定まる
やらないことを決めるプロセスは、必然的に「自分にとって何が重要か」を考えることにつながります。何をやらないかを決めることは、何を大切にするかを明確にすることでもあるからです。
例えば、「残業はしない」と決めるということは、「家族との時間を大切にしたい」という価値観の表れかもしれません。「ゴシップ話には参加しない」と決めるのは、「建設的な関係を重視したい」という価値観の表れかもしれません。
やらないことリストを作っていく中で、継続的に見直すプロセスを通じて、自分の価値観や人生の方向性がやらないことリストを作る前よりも明確になっていきます。
【実践編】やらないことリストの作り方5ステップ
ここからは、やらないことリストの具体的な作成方法について解説していきます。リストの作成手順は5ステップ。あなた自身の価値観に基づいたあなたのためだけのリストを作っていきましょう。
ステップ1:現在の行動を全て書き出して現状把握
まずは、自分が普段どのような行動をしているかを客観視することから始めましょう。1週間程度、以下のような項目について記録をつけてみてください。
記録は完璧である必要はありません。大まかでokです。自分の行動パターンを把握することがこのステップの目的です。スマホのスクリーンタイム機能や、時間管理アプリを活用すると、比較的ラクに現状把握できます。
記録を取る際のコツは、判断や評価をせずに、まずは「事実」だけを書き出すこと。「無駄だった」「意味があった」などの感情は後のステップで整理するので、この段階では客観的な記録だけで問題ないです。
ステップ2:時間とエネルギーを奪う活動を特定
記録した内容を見返しながら、以下の基準で活動を分類してみましょう。
この分類作業で重要なのは、世間一般の価値観ではなく、あなた自身の価値観で判断することです。例えば、SNSが一概に悪いというわけではありません。情報収集や人との繋がりに価値を感じているなら、それはA分類かもしれません。
何を無駄とするか、判断する基準についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてお読みください。
ステップ3:自分の価値観と目標を明確化
やらないことを決める前に、まず「自分が何を大切にしたいのか」を明確にする必要があります。以下の質問への回答を考えてみてください。
質問への答えが、あなたの「やらないことリスト」を作成する際の判断基準となります。価値観は人それぞれ異なります。家族を最優先にしたい人もいれば、キャリアアップを重視する人もいるでしょう。唯一の正解はありません。素直な気持ちで答えることが何より大切です。
ステップ4:やらないことを具体的にリスト化
ここまでのステップを踏まえて、いよいよ「やらないことリスト」を作成します。ステップ2で「C」に分類した活動を中心に、以下のような形式でリスト化してください。
最初は3項目ほどから始めることをおすすめします。やらないことリストは、望ましくない現状を変えていくツールとなります。一度に多くのことを変えようとすると、負荷が大きすぎて挫折の原因になるためです。
ステップ5:代替行動を明確化
人間の脳は否定系を認識しづらい特性をもっています。「嫌な出来事を思い出さないでください」と言われると、かえって嫌な出来事について考えてしまうのと同じです。
最後のステップは、やらないことの代わりにやること=「代替行動」を明確にします。何かをやらないよりも、その代わりに何かをやる方が簡単だからです。
まず、ステップ4で作成した「やらないこと」リストについて、以下の質問を考えてみてください
否定系から肯定系に転換することで、やらないことリストはより実践しやすいツールに進歩させられます。
やらないことリスト具体例50選
やらないことリストの作り方を理解したところで、具体的にどのような項目をリストに入れればよいか迷う方も多いかもしれません。そこで、ここからは、多くの人に共通する時間とエネルギーの浪費要因を5つのカテゴリに分けて、合計50個の具体例をご紹介していきます。やらないことリスト作成の参考にどうぞ。
仕事・キャリア関連のやらないこと
- 目的の不明確な会議には参加しない
- 定時後の不急の業務連絡には即座に返信しない
- こだわって締切を遅らせない
- 他人の仕事を安易に引き受けない
- 意味のない資料作成に時間をかけない
- ゴシップや愚痴話に参加しない
- マルチタスクで複数の作業を同時進行しない
- 優先度の低いメールに即座に対応しない
- 自分のスキル向上に繋がらない雑務は断る
- 昼休みを仕事に使わない
人間関係・コミュニケーションのやらないこと
- エネルギーを奪う人との付き合いを続けない
- 他人との比較で自分を卑下しない
- 相手の問題を自分の問題として抱え込まない
- 曖昧な返事で相手を混乱させない
- 感情的になっている時に重要な話し合いをしない
- 相手を変えようとしない
- 過去の失敗を何度も蒸し返さない
- 相手の承認を得るために自分を偽らない
- 義理だけの付き合いを無理に続けない
- ネガティブな話題ばかりの会話を長引かせない
生活習慣・ライフスタイルのやらないこと
- 朝起きてすぐにスマートフォンをチェックしない
- 就寝前2時間以内にカフェインを摂取しない
- テレビをつけっぱなしにしない
- 買い物リストなしに買い物に行かない
- 疲れている時に重要な決断をしない
- 完璧な部屋の状態を維持しようとしない
- 毎日の服装選びに時間をかけすぎない
- 食事中にスマートフォンを見ない
- 無計画に休日を過ごさない
- 健康に良くないとわかっている習慣を続けない
デジタル・SNS関連のやらないこと
- 目的なくSNSをスクロールしない
- 通知が来るたびにすぐに確認しない
- 寝室にスマートフォンを持ち込まない
- 複数のSNSアカウントを同時に管理しない
- オンラインでの論争や炎上に参加しない
- 他人のライフスタイルと自分を比較しない
- 不要なアプリをダウンロードしない
- 動画配信サービスでだらだら視聴しない
- 手持ち無沙汰になってもすぐスマホを開かない
- オンラインショッピングで衝動買いしない
お金・消費行動のやらないこと
- セールだからという理由だけで買い物しない
- ブランド志向だけで商品を選ばない
- 予算を決めずに大きな買い物をしない
- 他人におごりすぎない
- 投資の勉強をせずに投資商品を購入しない
- コンビニで必要のないものまで買わない
- サブスクリプションサービスを放置しない
- 見栄のための出費をしない
- 家計簿をつけずに家計管理を曖昧にしない
- お金の話を避け続けない
自分に合った項目の選び方
これら50の具体例の中から、あなたの現在の状況や価値観に合致するものを3〜5個選んで試し始めることをおすすめします。
やらないことの選択は、以下の基準を参考にしてください
- 現在、実際に時間やエネルギーを奪われていると感じるもの
- やめることで明確なメリットが想像できるもの
- 比較的実践しやすそうなもの
やらないことリストを成功させるコツと注意点
やらないことリストを作成しても、実際に運用できなければ意味がなくなってしまいます。ここからは、やらないことリストを着実に自分の行動指針として固めていくためのコツを紹介していきます。
小さく始めて失敗を許容する
やらないことリストで最も多い失敗パターンは、「一度に多くのことを変えようとする」ことです。人間の脳は変化に対して強い抵抗を示すため、急激な変化は本能が拒絶反応を起こします。
まずは「25日間チャレンジ」から始めましょう。心理学的には、新しい習慣が定着するまでには最低21日間が必要とされています。25日間チャレンジはそれよりも余裕を持って進める方法です。最初の5日間は、5日のうちで1日だけ「やらないこと」に成功するよう心がけてください。残り4日は失敗してもokです。
例えば、「朝起きてすぐスマートフォンを見ない」という行動を、5日のうち1日だけできればokです。次の5日間は、5日のうち2日が目標ラインです。その次は5日のうち3日、と5日ごとに目標ラインを上げていきます。最終的に5日のうち5日とも行動できる=やらないことを定着させていきます。
この25日間チャレンジの狙いは、小さなハードルから始めて徐々にハードルを高くしていくこと、そしてミスを許容することです。思い立って行動を始めた時、自分への期待は膨れ上がっていることが多いです。しかしそれと同時に失敗する可能性も一番高いです。今までやったことないことにチャレンジしようとしてるので当然ですね。そして自分に期待してる分、失敗した時のショックが大きくなります。これが新しいことを始めた時に挫折する根本原因の一つです。
なので、成果を期待する気持ちも分かりますが、それを意図的に抑えて、失敗を許容する。そのための25日間チャレンジです。
周囲の理解を得るコミュニケーション
やらないことリストの実践は、たまに周囲の人との摩擦を生むことがあります。今まで引き受けていた依頼を断るようになったり、参加していた集まりに参加しなくなったりすると、相手に不快感を与えることもあります。
重要なのは、個人的な価値観の問題であって、相手を批判しているわけではないことを明確にすることです。「そういう集まりは意味がない」ではなく、「私にとって今は優先度が低い」という伝え方をしましょう。
職場での実践方法については特に注意が必要です。上司や同僚に対して「やらないことリスト」の存在を説明する際は、「より効果的に貢献するため」という建設的な意義を見出した方が理解が得られやすいです。
挫折しがちなパターンと対策法
パターン1:完璧主義
一度でもリストを守れなかった時に「もうダメだ」と諦めてしまう方は、完璧主義かもしれません。
「カウンターマインド」を身につけましょう。カウンターマインドとは、「失敗した次の日こそ、もう一度始める最大のチャンス日」と捉える心構えのことです。失敗した次の日、今日またリストを守り始められたら、それは[失敗してもまた始められた実績]になります。この実績は、次同じような場面に出くわしたとき、(前できたから今回もできるわ)と自分を後押しする自信になります。
パターン2:周囲からの圧力に負ける
家族や同僚からの「付き合いが悪い」といった批判に屈してしまう方が、これに当てはまります。
事前に信頼できる人に自分の取り組みについて説明し、サポートを得ておくことが肝要です。また、「なぜこの取り組みが自分にとって重要なのか」を明文化し、ブレそうになった時に読み返せるようにしておくのも対策になります。
パターン3:効果が実感できない
短期間で効果を期待しすぎて、効果が見えないと継続をやめてしまう、いわゆる「三日坊主」です。
効果の実感方法を事前に決めておきましょう。時間の使い方、ストレスレベルの変化、達成できたことなどの記録、客観的な指標をつくって定期的にチェックするようにします。小さな変化にも気づけるよう、成果を振り返る時間を確保することも大切です。
パターン4:新しい誘惑への対応
リストにない新しい時間の浪費要因が現れた時に対応できないパターンです。例えば、付き合いでなんとなく行ったパチンコにハマってしまった、などです。
「判断基準」を明確にしておくことが重要です。新しい誘惑が現れた時に、自分の価値観に照らし合わせて判断できる基準を持っておけば、リストにない事柄でも適切に対応できます。
よくある質問
- Qやらないことが思い浮かばない。どうすればいい?
- A
まずは、やらないことリスト具体例50選を参考に、自分に必要なくてやめたいと思っている事を探してみてください。他には、1週間、「疲れた」「時間の無駄だった」と感じた瞬間をメモしてください。それがあなたの「やらないこと」候補になります。また、「本当はやりたくないけど、断れずにやっていること」を思い浮かべてみましょう。
- Q家族から「付き合いが悪い」と批判される。対処法は?
- A
「家族との時間をもっと大切にしたいから、他のことを整理している」と目的を明確に伝えましょう。批判の背景には「一緒の時間が減る不安」があります。実際に家族との時間が増えることを行動で示し、時間をかけて信頼関係を築くことが大切です。
- Q職場で断ると評価が下がるのではないかと心配。
- A
個人的理由ではなく「業務効率向上」「成果の最大化」という観点で説明しましょう。「より重要な業務に集中するため」と伝え、必ず代替案も提示してください(「会議には参加できませんが、議事録で内容確認します」など)。小さな案件から始めて信頼を積み重ねましょう。急がば回れです。
- Qリストの項目が多すぎて管理できない。
- A
優先度で分類してください:A(絶対やらない・5項目以内)、B(なるべくやらない・10項目以内)、C(状況判断)。また、複数項目をまとめることも有効です。例:「SNSを見ない」「テレビを見ない」→「受動的な娯楽に時間を使わない」。3ヶ月に1回程見直して、定着した項目は卒業させましょう。
- Q効果が実感できない。どのくらい続ければいいのか?
- A
効果は段階的に現れます。1週間後に時間の余裕、1ヶ月後にストレス軽減、3ヶ月後に生活パターンの安定、6ヶ月〜1年後に人生の質的変化というように徐々に実感していくのが一般的です。空いた時間の活用方法、ストレスレベルの変化、達成した目標などを記録して、小さな変化への感度を高めることも有効です。
まとめ
今回は、忙しい現代人に向けて、やらないことリストという時間管理術について詳しく解説しました。
- やらないことリストは「引き算の発想」で限られた時間を大切なことに集中させるツール
- 時間の余裕創出、ストレス軽減、意思決定疲れの軽減、価値観の明確化という4つの効果がある
- 現状把握→時間泥棒の特定→価値観明確化→具体的リスト化→代替行動設定の5ステップで作成
- 小さく始めて失敗を許容し、周囲の理解を得ながら継続することが成功の鍵
やらないことリストを実践することで、あなたは本当に大切にしたいことに時間とエネルギーを注げるようになります。時間に追われる毎日から、自分の価値観に基づいて主体的に時間をコントロールする充実した人生へと変化していくでしょう。
まずは本記事で紹介した具体例50選の中から、あなたの現状に当てはまるものを3項目選んで、25日間チャレンジから始めてみてください。小さな一歩が、あなたの人生を大きく変える第一歩となります。
やらないことリストの他、多忙な毎日を和らげる工夫をさらに知りたい方は、こちらの記事もどうぞ。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。