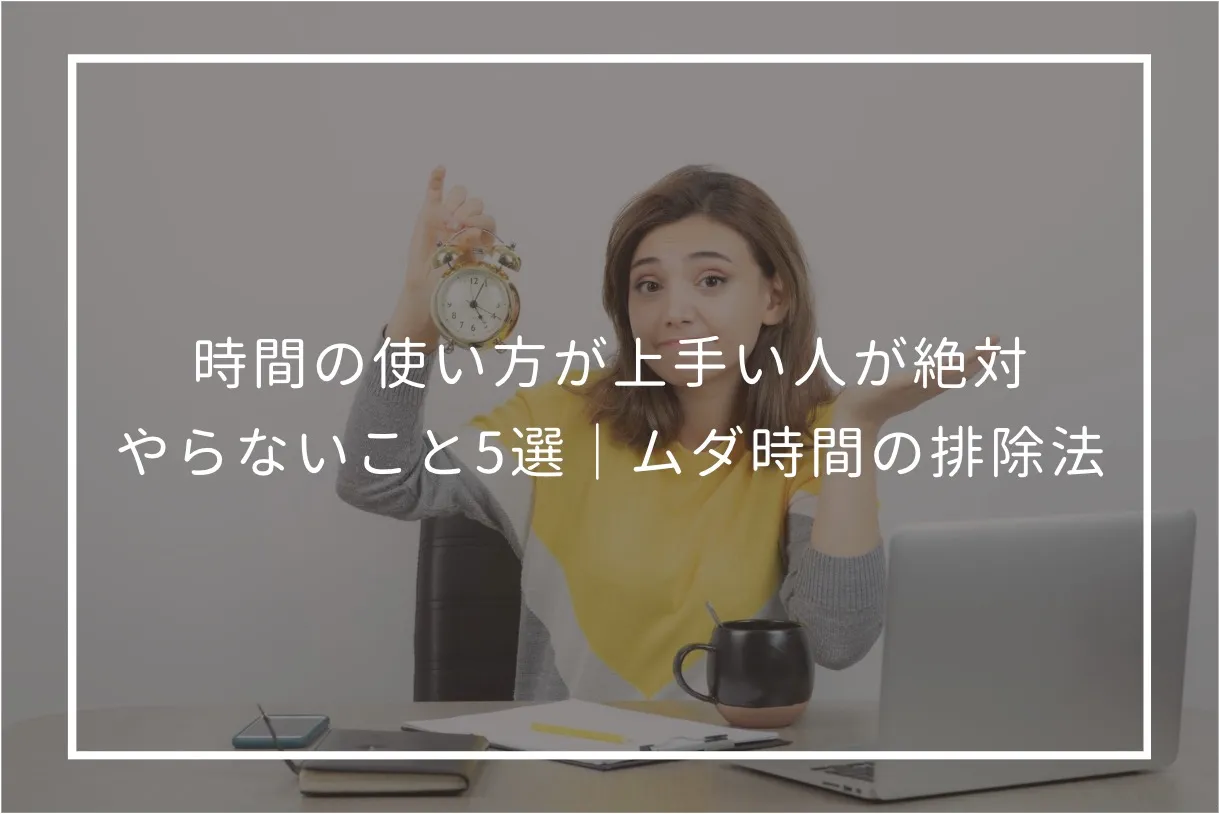けうzenです。
今回は、時間の使い方を改善したい方に向けて、時間の使い方が上手い人が絶対やらないこと5選と、今日から実践できるムダ時間の排除法をご紹介します。
毎日忙しく過ごしているのに、夜振り返ると「今日は何をしたんだろう…」と虚しさを感じる。やりたいことがあるのに時間が足りない。そんな悩みを抱えてはいないでしょうか。
実は、時間の使い方が上手い人とそうでない人の違いは、能力の差ではありません。
「何をやるか」ではなく「何をやらないか」を明確に決めているかどうかの差なのです。
この記事では、時間の使い方が上手い人が絶対にやらない5つのことを具体的に解説します。
さらに、ムダ時間を排除するため、今日から実践できる7つのアクションも紹介していきます。
時間に追われる毎日から、時間をコントロールする毎日へ。その第一歩を踏み出したい方は、ぜひ読み進めてください。
それでは、どうぞ!
時間の使い方が上手いとは?
時間の使い方が上手い人の定義
そもそも、時間の使い方が上手い人とは、どんな人のことなのか?
まずは今目指そうとしてる人の特徴について理解しなければ、目指すも何もないでしょう。
時間の使い方が上手い人は、3つの特徴を持っています。
1. 目的認識力が高い
何のためにその行動をするのか、目的を常に明確に理解しています。「なんとなく」「みんながやっているから」という理由で行動することはありません。すべての行動に「なぜ」があり、その「なぜ」を自分の言葉で説明できる状態です。
例えば、会議に参加する際も「この会議の目的は何か」「自分がいる意味はあるか」を考えます。目的が不明確なら参加を見送る判断もできます。
2. 行動設計力が高い
目的を理解した上で、それを達成するための行動を設計できます。目的を達成するために適した行動を選択して、できる限りムダなく後戻りなく、目的に到達できる道筋を描くことができます。
予定変更や緊急事態に柔軟に対応できる調整力も、行動設計力の一部です。予定通りに進まないことを前提に、余裕を持った予定・ペースの設定ができます。
3. 自己管理能力が高い
意識を向ける対象を自分でコントロールできます。集中すべき時に集中して、休むべき時に休む。この切り替えが上手です。
意識を向け続けられるよう、自分を置く環境を調整できます。スマホを別の部屋に置く、通知をオフにする、作業に適した場所を選ぶなど、自分が目の前のこと集中できる環境を意図的に作り出します。
この自己管理能力の高さが行動の効率につながり、行動の効率が余裕を作ります。そして、余裕があるからこそ、目的認識や行動設計に時間を使え、好循環が生まれます。
これが、時間の使い方が上手い人が持つ3つの力です。そして、これらの力は訓練次第で誰でも身につけられるものでもあります。
「充実している」と「忙しい」の違い
同じように予定がぎっしり詰まっていても、「充実している」と感じる人と「忙しい」と感じる人がいます。この違いは一体どこにあるんでしょうか。
その答えは、やるべきことの見極めにあります。
充実している人は、何でもかんでも「やるべきこと」にはしません。自分にとって本当に重要なこと、目的に沿ったことだけを選別して、それ以外は手放しています。
一方、忙しい人は、降ってくるタスクをすべて引き受けてしまいます。他人からの依頼、緊急に見える案件、「やった方がいいかも」というレベルのことまで、すべて「やるべきこと」に加えがちです。
忙しい人は、時間に追われ、振り回され、余裕がありません。次から次へとタスクに追いかけられ、常に後手です。
対して充実している人は、1日を自分でデザインします。主導権を握ろうとします。重要なタスクに集中時間を確保し、余裕を作り出そうとします。その過程で断るべきことをしっかり断ることができます。
結果として、時間に追われることなく、自分のペースで物事を進めています。
忙しい人は受動的に時間を消費し、充実している人は主体的に時間の手綱を握っている。これが違いです。
やらないことを決める重要性
「やることリスト」を作る人は多いですが、「やらないことリスト」を作る人は少ないのではないでしょうか。時間の使い方が上手い人ほど、やらないことを明確に決めています。
やらないことを決めるのは、先述の行動設計力に強く関係します。
人間の時間とエネルギーは有限です(今のところ)。すべてをやろうとすると、本当に重要なことに十分な時間とエネルギーを注げなくなります。
やらないことを決めるということは、目的に沿った行動を選別する行為でもあります。自分の目的や価値観に照らし合わせて、「これは今の自分には必要ない」「これは他の人に任せられる」と判断を下す行為です。
例えば、「資格取得」という目的があるなら、飲み会への参加頻度を減らすと決めるかもしれません。「健康的な生活」が目的なら、夜更かしをしないと決めるでしょう。
やらないことを決めるもう一つ大きなメリットは、誘惑や他人の依頼に対する判断基準が明確になることです。
突然の誘いや依頼があった時、やらないことリストに照らし合わせて判断できます。「これは自分がやらないと決めていることだ」と分かれば、迷わず断れます。
総じて、やらないことを決めることは、行動設計力を高めます。ということはつまり、上手い時間の使い方につながるということです。
では、時間の使い方が上手い人は、どんなことをやらないことに決めているのでしょうか。
時間の使い方が上手い人がやらないこと5選
ここからは、時間の使い方が上手い人が絶対にやらない5つのことを紹介していきます。
目的なくSNSやYouTubeをダラダラ見る
時間の使い方が上手い人は、SNSやYouTubeを「ちょっとだけ」のつもりで開くことはしません。
SNSやYouTubeのアルゴリズムは、人を飽きさせない設計になっています。大して興味もないけどなぜか見続けて、気づいたら1時間、2時間と経ってた…なんてことはザラです。
目的なく見始めると、本来やるべきだったことをあっさりすっぽかします。そして(自分はなんてダメなんだ…)と自己嫌悪モードに。
それだけじゃなく、無駄な情報で頭がいっぱいになったりもします。
良いことなんてほとんどないと分かってるのに、それでも見てしまう。この状況は時間の使い方が上手いとは言えないでしょう。
時間の使い方が上手い人は、SNSやYouTubeを見る時間や目的を明確に決めています。「昼休みの10分だけ」「通勤時間の10分だけ」と、状況をセットにして物理的に時間を区切ってます。
あなたのスマホのスクリーンタイムを確認してみてください。自分が思っている以上に時間を費やしていることに驚くはずです。
期限を決めずにタスクに取り掛かる
時間の使い方が上手い人は、タスクに期限を設定します。「いつか終わればいい」という曖昧なイメージでは取り掛からないのです。
これは、パーキンソンの法則を理解しているからです。
イギリスの歴史学者シリル・ノースコート・パーキンソンが1958年に提唱した、仕事は「与えられた時間をすべて使うように広がる」という法則。必要以上に作業が引き延ばされやすく、締め切りが遠いほど効率が下がりやすいという人間の傾向を示している。
期限がないと緊急度が低いので、他のタスクに押し出されて永遠に完了しないことも多いです。「そのうちやろう」と思っていたことが、何ヶ月も放置されている経験は誰にでもあると思います。
時間制約がないので集中できず、必要以上に時間をかけてしまいます。本来なら3日で終わるはずのタスクに気づいたら1週間経ってたなんてことも起こり得ます。
期限を決めるとはつまり、終わりを決めるということです。終わりを決めれば、そこに辿り着くために終わりから逆算して、この地点にいつまでに辿り着くという中継地点を設置していけます。
時間の使い方が上手い人は、タスクに自分で期限を設定し、時間を区切って作業します。他人から期限を指定されていないタスクでも、例えば自分で「今日の17時にココまで」と決めて取り組みます。
長電話や雑談に付き合いすぎる
時間の使い方が上手い人は、長電話や雑談に付き合いすぎないようにしています。
長話の全く意味がないわけではありません。話を聞くこと、気にかけることは良い人間関係の土台です。
ただ、頻繁に会話に時間を使いすぎても、相手の時間を奪うことにもつながるし、自分も本来やりたかったことに注ぐはずだった時間を不意にしてしまいます。
相手がもっと話したそうな時は「断ったら感じが悪いと思われるかも」「相手を傷つけたくない」という心理があるかもしれません。がしかし、自分の時間を守ることは、相手への配慮でもあり自分への配慮でもあるのです。
時間の使い方が上手い人は、明確に、それでいて丁寧に会話を切り上げるスキルを持っています。
決して失礼なことではありません。むしろ、お互いの時間を大切にする誠実な態度です。
夜更かし
夜更かしは、翌日の時間・気分・生産性を大きく損なう、悪循環の始まりだと、時間の使い方が上手い人は知っています。
睡眠不足は、判断力、集中力、記憶力を低下させることが研究で示されています。
夜遅くまで起きていても、実は大して生産的なことはできません。大抵の場合、SNSやテレビを見ているだけ、あるいはベッドでスマホをいじっているだけです。疲れてる頭で良い判断も作業もできません。
夜更かしすると、翌日、いつもなら2時間で終わる仕事に4時間かかってしまうこともあります。結果として、さらに時間が足りなくなって、また夜更かしする悪循環に陥りかねません。
朝の時間帯は、脳が最もクリアで生産性が高いゴールデンタイムです。夜更かしする人はこの貴重な時間を失っています。
「夜の方が集中できる」と思っている人もいるかもしれません。しかしそれは、静かで邪魔が入らないからであって、脳のパフォーマンス自体は朝の方が圧倒的に高いです(夜型の人は除く)。
時間の使い方が上手い人は、朝時間を最大限活用するため、夜は明日のための準備時間と割りきって、しっかり休むことを優先しています。
準備に時間をかけすぎる
準備に時間をかけすぎると、実行に移すまでに時間がなくなったり、モチベーションが下がったりします。完璧な準備を求めるあまり、「準備している自分」に満足して実践に進めなることもあります。
情報収集や計画立案に何時間もかけても、実際にやってみなければ分からないことが大半です。頭の中でいくらシミュレーションしても、現実は想定と違うことばかり。準備8割、実行2割のような時間配分では、実践から学ぶ機会が少なくなります。準備している間に状況が変わったり、機会を失ったりすることもあります。
時間の使い方が上手い人は、最低限の準備でとりあえず実行に移します。不完全でも良いからまず形にして、フィードバックを得ながら改善していくアプローチを取ります。
「準備不足で失敗したらどうしよう」という不安は誰にでもあります。しかし、準備した通りに物事が運ぶことがいったいどれだけあるでしょうか。要するに、完璧な準備というものは存在し得ないということです。小さく始めて、小さく失敗して、改善していく。この繰り返しが、結局一番効率的が良かったりします。
今日からできること
ここまで、時間の使い方が上手い人の特徴、そして絶対やらないことを見てきました。
さて、時間の使い方が上手くなるために、今できることは何でしょうか。具体的に何から始めればいいのでしょうか。
ここからは、時間の使い方が上手くなるために、今日から実践できる7つのアクションを紹介します。
1日の時間の使い方を一度記録する
まず最初にできることは、自分が何に時間を使っているか客観的に把握することです。スタート地点は、現状を知ることから始まります。
タイムトラッキングアプリを使って、1日の自分の時間の流れを記録してみましょう。
記録して、自分の時間の使い方を見える化すると、特有のパターンや傾向が見えてきます。
「朝はダラダラしがち」「午後3時以降は集中力が落ちる」「夜にSNSを見る時間が長い」など、どの時間帯が思い通りに動けてるのか、もしくは思い通りに動けてないのか、明確になります。
思い通りに動けてない時間は、無意識なことがほとんどです。「こんなに時間を使っていたのか」と、無意識な時間の使い方に気づくことは、行動変容の第一歩になります。
多くの人は、自分の時間の使い方を感覚でしか把握していないです。どんな時間の使い方をしているのか、どこに改良の余地がありそうか、記録を取ることで見えるようになっていきます。
まずは、騙されたと思って自分の1日を記録してみてください。
時間泥棒トップ3をリストアップする
記録したデータから、自分の時間を最も奪っている活動を3つ特定しましょう。これが、あなたの「時間泥棒トップ3」です。
多くの人にとって、SNS、YouTube、ダラダラとテレビ視聴が上位に入ります。しかし、時間泥棒は人によって異なります。ゲーム、ネットサーフィン、意味のない会議、長電話など、さまざまなパターンがあります。
トップ3を特定できれば、対策を立てやすくなります。「なんとなく時間が足りない」という漠然とした悩みが、「SNSに1日2時間使っている」というように、具体的な課題点に変わります。これを『悩みの解像度が高まる』と言います。
悩みの解像度が高まると、具体的な対策を考えやすくなります。
「なんとなく時間が足りない」のように漠然と悩んでいた時は、「テキパキ行動する」というように具体的に何をするのかわからないような対策しか考えられません。
これが「SNSに1日2時間使っている」と悩みの解像度が上がると、「SNSアプリの使用時間制限機能をONにする」「SNSアプリを1日90分しか開けない設定にする」というように具体的な行動に落とし込みやすくなります。
行動の具体性が増すと、当たり前ですが悩みを解消できる可能性も増します。
時間泥棒トップ3をリストアップして、悩みの解像度を高めていきましょう。
スクリーンタイムを設定する
時間泥棒の多くは、スマホから来ています。スマホの使用を制限する仕組みを作ることが効果的です。
iPhoneの「スクリーンタイム」やAndroidの「Digital Wellbeing」で、アプリごとの使用時間制限を設定しましょう。SNSアプリを1日30分、YouTubeを1日1時間など、時間で制限をかけます。
時間制限に達すると通知が来たり、アプリが使えなくなったりするので、強制的に使用を止められます。意志の力に頼るのではなく、システムで制限するのがポイントです。
制限設定のポイントですが、最初は超ゆるめの制限にするのがおすすめです。
まずは制限を守ることに成功してください。成功できるくらい緩い制限にしてください。
なぜか?
いきなりきつい制限をかけると十中八九失敗します。
今までの自分から見れば多少なりとも努力しているのに失敗するんです。
失敗が続けば、(自分は自分で決めたことも守れないダメな人間だ)ということを何度も認識するためだけの制限になってしまいます。努力してるのにも関わらず。
そんなものが続くはずがありません。
なのでまずは成功することが大事なんです。
一度成功すれば、それは大きな前進です。今の制限が普通になってきたら、少し制限をキツくする。この繰り返しで成長していけます。
スマホの使用時間を減らしていくため、まずは超ゆるめのスクリーンタイム制限から始めていきましょう。
タスクに2段階期限を設置する
1つのタスクに「挑戦期限」と「最終期限」の2つの期限を設定しましょう。挑戦期限は最終期限よりも前に設置する、文字通り挑戦する期限です。最終期限は絶対に終わらせなければならない日時です。
挑戦期限を設置して、ギリギリまで先延ばしにする癖を防げます。人間は締め切りがあると、その時間いっぱいまで使ってしまう傾向があります(パーキンソンの法則)。挑戦期限という早めの目標を設定することで、この心理を逆利用します。
小さなタスクごとに「今日15時まで」「明日の午前中まで」と、具体的な時間を設定してください。
2段階期限により、万が一遅れても最終期限までにリカバリーする余地を残せます。
タスク管理ツールやカレンダーに2つ期限を書き込んで、視覚的に認識できるようにしてください。
話の切り上げ方を習得する
会話の切り上げ方を身につけましょう。
最もシンプルな方法は、「そろそろ次の予定があるので」と正直に伝えることです。嘘をつく必要はありません。あなたには次にやるべきことがあるはずです。
「またゆっくり話しましょう」と前向きな態度を示すと、相手に不快に思わせることはほとんどないはずです。会話を拒否しているのではなく、タイミングの問題だと伝わります。
長話になりそうだと感じたら、最初に「今10分しか時間がないんです」とあらかじめ断りを入れておくといいです。
立ち話の場合、「では、また」と、話の切れ目で会話を終わらせるのがシンプルかつあれこれ考えなくて済みます。
断ることは悪いことではありません。むしろ、お互いの時間を大切にする行為です。相手もあなたの時間を奪いたいわけではないと思います。この認識を変えるだけで、会話を切り上げることへの罪悪感が消えます。
一度やってみると、ほとんどの人は気にしていないことに気づくでしょう。
寝床に就く時間を全ての基準にする
「夜更かし」をやめるために、起床時間ではなく就寝時間を固定しましょう。その就寝時間を1日のスケジュールの基準にします。
例えば、24時に寝ると決めたら、23時半には準備を始め、22時には作業を終える計画を立てます。逆算して1日のスケジュールを組めば、夜のダラダラ時間を防ぎやすくなります。
そして、十分な睡眠は翌日の生産性を最大化する最も確実な方法です。睡眠を削って作業するより、しっかり寝て翌朝集中する方が、はるかに効率的です。
「今日中に終わらせる」という曖昧な期限ではなく、22時までという明確な期限ができます。「24時に寝るから、このタスクは22時までに終わらせる」と、時間の使い方が明確になります。
就寝前のルーティン(読書、ストレッチ、明日の準備など)を決めると、ルーティンをトリガーに自然と体が寝る準備を始めます。ルーティンが睡眠のスイッチになり、寝つきも良くなります。
決めた時間に寝ることを最優先にしてみてください。朝の目覚めが変わって、1日の生産性が向上することを徐々に実感できるはずです。
とりあえず取りかかる
準備を完璧にする代わりに、まずは5分だけ手を動かしてみてください。
「完璧な準備ができてから」と考えているうちは、いつまでも始められません。60%で一度形にしてから修正する方が、結果的に早いです。しかも出来も良かったりします。
「とりあえず5分」「とりあえず1ページ」など、最小単位から始めることを意識します。
実践しないと見えてこないもの、実践することでのみ見えてくるものがあります。こればかりは頭の中でいくら考えても分かりません。
これはつまり、始める前から全てを見通すような完璧な準備は、原理的に不可能ということです。実践しないと見えてこないものがあるからですね。
今日やろうと思っていることがあるのなら、まずは始めて5分だけやってみましょう。
準備は後からでも間に合います。というより、やってからしか見えてこないものは準備のしようがありません。
まずは、とりあえず取りかかることです。
まとめ
今回は、時間の使い方が上手くなりたい方に向けて、時間の使い方が上手い人が絶対やらないこと5選と、今日から実践できる改善方法について解説しました。
- 時間の使い方が上手い人は「目的認識力」「行動設計力」「自己管理能力」の3つの力を持っている
- 「充実している」と「忙しい」の違いは、やるべきことを見極められるかどうか
- やらないことを決めることで、行動設計力が高まり時間の使い方が上手くなる
- 時間の使い方が上手い人がやらないこと
- ① 目的なくSNSやYouTubeをダラダラ見る
- ② 期限を決めずにタスクに取り掛かる
- ③ 長電話や雑談に付き合いすぎる
- ④ 夜更かし
- ⑤ 準備に時間をかけすぎる
- 改善の第一歩は「1日の時間の使い方を記録する」こと
- スクリーンタイム設定、2段階期限設定、就寝時間の固定など、仕組みで時間をコントロールする
時間の使い方が上手くなるということは、単にたくさんのことをこなせるようになることではないです。
自分にとって本当に重要なことに時間を使い、充実感を持って毎日を過ごせるようになることです。
今まで「なんとなく時間が足りない」と感じていたのは、無意識のうちに時間泥棒に時間を奪われていたからかもしれません。
この記事で紹介した「やらないこと」を意識して排除していけば、時間に余裕を持ちやすくなります。
今日紹介した7つのアクションから、まずは1つだけ選んで実践してみてください。どれか1つで構いません。時間の使い方を変える大きな変化の始まりになります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。