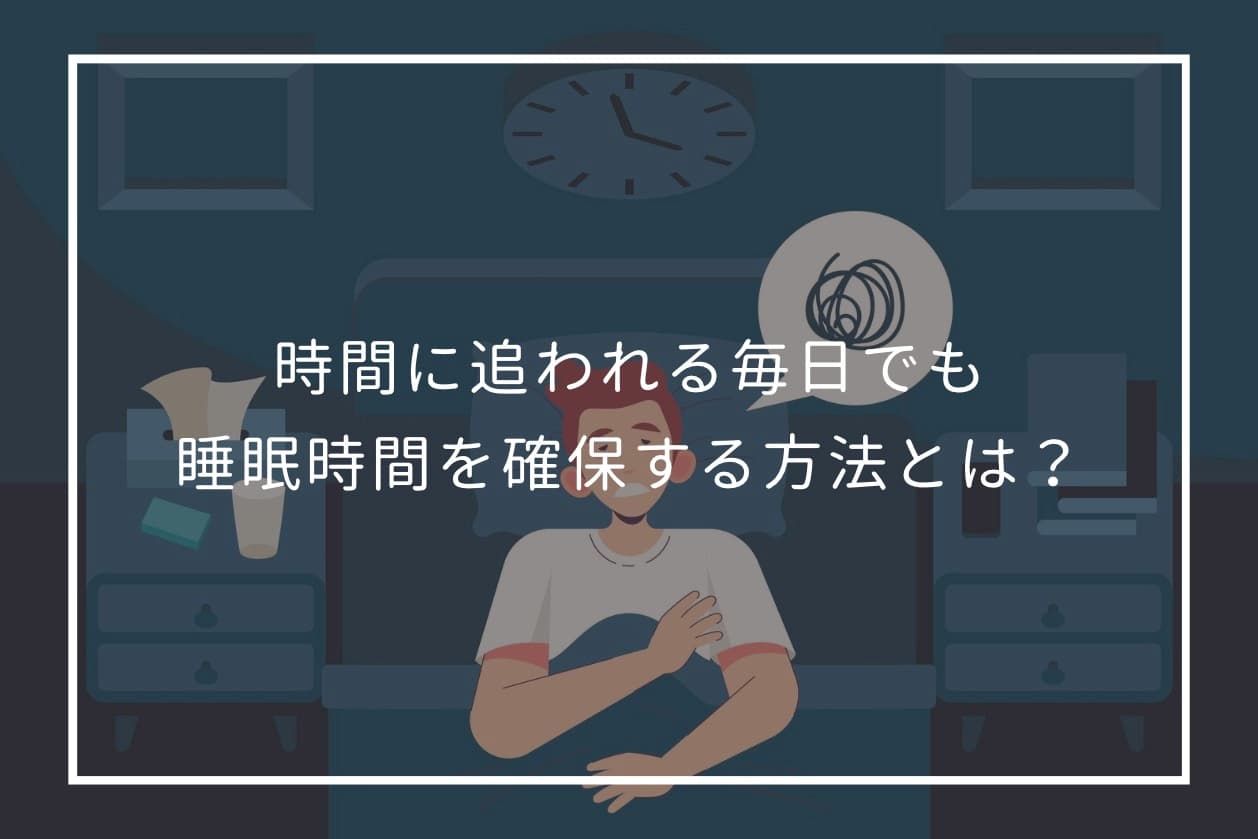けうzenです。
毎日「今日こそは早く寝よう」と思っても、気づけば深夜。タスクは山積みで、周囲に配慮するあまり自分の時間を削り、気がつけば慢性的に睡眠不足。そんな毎日にお悩みではないでしょうか。
朝から疲れて頭はぼんやり、感情の余裕もなくなり、ますます時間に追われる悪循環に陥ってしまいます。
もしその悩みが、意外とシンプルな工夫で変えられるとしたら…どうでしょうか。
この記事では、時間に追われる毎日でも睡眠時間を確保する方法と、現実の制約を乗り越える具体的な工夫を紹介します。時間に追われる日々の中で、睡眠をしっかり確保しながら自分らしい生活を取り戻すヒントをお伝えしていきます。
時間に追われる毎日でも、睡眠時間を取り戻すための一歩を、一緒に踏み出していきましょう。
それでは、どうぞ。
なぜ、毎日睡眠時間が削られるのか
「今日こそは早く寝よう」と思いながら、気づけばまた深夜になっている。毎晩この繰り返しではないでしょうか。
真面目で責任感の強いあなたは、すでに少なからず工夫や努力を重ねてきたはず。それでも、睡眠時間だけは確保できないのはなぜなのか。
まずは、毎日睡眠時間を削られる原因を見ていきます。
そもそも全体の作業量が多すぎる
あなたが時間に追われる毎日に陥ってしまっているのは、そもそも抱えているタスクの総量が1日の時間に対して多すぎるからかもしれません。
「これくらいできなきゃ回らない」と無意識に最低ラインを引いている場合もあるでしょう。
人にはいろんな立場があります。管理職として、部下として、上司として、社会人として、親として、子として、人として、それぞれの立場からやるべきだと抱えているものがあるでしょう。
しかし私たちはあらゆる有限なものに囲まれて生きています。時間、体力、集中力、どれも有限です。有限なものに対して、抱えているタスクが多すぎるのです。
ありきたりな原因かもしれませんが、放置していいものではないでしょう。
自分の時間を犠牲にして周囲に配慮している
あなたが責任感の強い性格の場合、家族や職場に迷惑をかけたくない気持ちで、自分の時間を削って調整することがあるかもしれません。
職場では「この仕事、明日の朝一番でお願いします」と言われれば、本来なら「時間が足りません」と言うべき状況でも、「分かりました」と受け入れて、夜中まで作業する。パートナーが疲れていれば、本来分担するはずの家事も引き受ける。
他者への配慮は素晴らしいことです。しかし、その配慮は『自己犠牲』を前提に成り立っていないでしょうか。周囲への配慮が常態化すると、「自分の時間を削ればいい」となって、結果的に時間に追われる日々をつくる根因となってしまいます。
構造的に睡眠時間を削らざるを得ない状況
一番深刻なのは、どんなに工夫しても睡眠時間を削らないと間に合わない状況が構造的に続いている状態です。
残業が前提となってる職場で働いていれば、どんなに効率化しても定時で帰ることは自然と難しくなっているでしょう。小さなお子さんがいる家庭では、子どもに関わる時間を削ることができません。資格取得や昇進のために学習時間が必要で、それを確保するには睡眠時間を削るしかない状況もあるでしょう。
こうした構造的な問題がある限り、個人の努力だけでは限界があります。しかし、だからといって睡眠時間を削り続けることが得策とはいえません。
睡眠時間を削るメリット・デメリット
睡眠時間を削ることで、確かに短期的には得られるものがあります。しかし、その代償として失っているものの大きさは、その場では気づきにくいものです。
睡眠時間を削って得られるメリット
なんとか間に合わせられた安堵感
締切が迫ったタスクを夜中まで作業して完成させたときの「間に合った」という安堵感は格別です。「ありがとう。」「頑張ったね、お疲れ様。」と言われる瞬間は、報われた気持ちでいっぱいになることでしょう。
「今日もなんとか乗り切れた」という感覚は、明日への不安を一時的に和らげてくれます。
家族や同僚からの「頑張っている」という評価
睡眠時間を削ってまで家族のために尽くしたり、職場の期待に応えたりする姿は、周囲から高く評価されます。「いつも遅くまでお疲れ様」「頼りになる」といった言葉に、自分の価値を実感している方もいるでしょう。
特に責任感の強いあなたにとって、周囲からの信頼と感謝は大きなモチベーションの源になっているはず。
資格試験や昇進に向けた学習時間の確保
キャリアアップのための資格取得や、昇進試験の準備において、睡眠時間を削ることで学習時間を生み出せます。「他の人が寝ている間に努力している」という優越感も、原動力になります。
将来への投資として、一定期間の睡眠不足は必要な犠牲だと考える人も多いでしょう。
睡眠時間を削って被るデメリット
朝起きた瞬間から疲れている
目が覚めた瞬間、「まだ眠い」「体が重い」「今日も長い一日が始まる」という憂鬱な気持ちに襲われる。朝から既に疲れている状態では、1日を前向きに始めることができません。
本来なら「今日もがんばろう」と思えるはずの朝の時間が、「なんとか乗り切ろう」という後ろ向きな気持ちになります。
終日頭がボーッとしている
睡眠不足の影響は、その日の間中続きます。普段なら5分で決められることに15分かかる。メールの返信一つでも、何度も読み返さないと内容が頭に入らない。重要な連絡をすっぽかして、リカバーにさらに時間が必要になる。
思考に霧がかかったような状態が続いて、本来30分で終わる作業が1時間要し、結果的にさらに夜時間を圧迫する悪循環が始まります。
些細なことでイライラしてしまう
睡眠不足では感情のコントロールも難しくなります。頭のリソースに余裕がないため、子どもの些細な質問にイライラして強く叱ってしまったり、同僚のちょっとしたミスに過剰に反応してしまったり。普段なら笑って流せることが、大きなストレスに感じられます。
後で「なんであんなに怒ってしまったんだろう」と後悔、自分で自分の精神的な負担を増やすことになってしまうことも。
風邪をひきやすくなる
睡眠不足状態は免疫力が下がっています。風邪やインフルエンザにかかりやすくなります。厄介なのは、睡眠不足の状態では回復にも時間がかかることです。
普段なら2-3日で治る風邪が1週間長引く。体調不良で仕事のパフォーマンスが下がり、さらに余裕がなくなる。睡眠時間を削って得た数時間よりも、はるかに多くの時間を無駄にする可能性が結構あります。
これらのメリットとデメリットを天秤にかけたとき、睡眠時間を削ることで得られるメリットは、長期的に見て失っているものに比べてあまりにも小さくないでしょうか。
「時間の確保」という観点では、睡眠時間を削ることは逆効果といえるでしょう。睡眠不足により失う時間の方が、削って得た時間よりもはるかに多いからです。
時間を確保したいなら、むしろ睡眠時間をしっかり確保することから始める必要があります。
睡眠時間確保の原則
睡眠時間確保の具体的な方法に入る前に、まず基本的な原則について軽く確認していきます。
ただ闇雲に思いつきを行動に移しても効果がない・思うように続かないことが多いのではないでしょうか。
それは、「睡眠時間確保の原則」から外れた行動になってるからと考えられます。
なので、まずは以下の「睡眠時間確保の原則」を一度確認することから始めていきましょう。
1つずつ見ていきます。
睡眠時間の「量」が全ての土台
睡眠について語られる際、「質の高い睡眠を」「短時間でも深く眠れば」といった話をよく耳にします。しかし、時間に追われているあなたがまず最優先すべきは、睡眠の「量」の確保です。
睡眠の質を高める工夫は、十分な睡眠時間が確保できてから取り組むものです。2、3時間しか眠れていない状態で睡眠の質を追求しても、根本的な解決にはならないとされています。(参考:知って快眠!睡眠の新常識)
まずは必要な睡眠時間をしっかり確保する。これが全ての土台となります。
あなたに必要な最低限の睡眠時間を知る
「目標睡眠時間はコレ」とよく言われますが、必要な睡眠時間は個人差があります。あなたが機能するために必要な最低限の睡眠時間を見極めることが重要です。
6時間でも日中しっかり集中できて、イライラせずに過ごせる人もいれば、7時間は確保しないと午後にパフォーマンスが落ちる人もいます。大切なのは、世間の基準ではなく、あなた自身の体が求める睡眠時間を把握することです。
それ以上削ると、翌日のパフォーマンスに明らかに影響が出る境界線を見つけることが次へのステップです。
今の生活パターンにフィットしていること
睡眠時間確保において次に重要なのは、あなたが現在送っている生活パターンにフィットしていることです。
夜勤がある仕事をしているなら、世間一般の就寝時間に合わせるのは無理があるでしょう。小さなお子さんがいて早朝に起こされる生活なら、その状況に合わせて工夫する必要があります。平日と休日で生活リズムが異なっているなら、それぞれの実情に応じた睡眠時間確保を目指す方向性が柔軟で続けやすいでしょう。
大切なのは、あなたの現在の生活の中で「これなら確実に実行できる」と思える設定にすることです。生活パターンを大幅に変えようとするのではなく、今の生活の流れの中で睡眠時間を確保する方法を見つけることが先決です。
睡眠時間は「削れない時間」として扱う
睡眠時間確保の原則、その中で最も重要な原則は、睡眠時間を「調整可能な時間」ではなく「削れない時間」として扱うことです。
人は食べないと生きていけません。飲まないと生きていけません。それと同じように、眠らないと生きていけないのです。
人間が他の野生動物と生存競争をしていた太古、いつ他の生物に襲われるか分からない状況でした。そんな世界で意識がなくなるという圧倒的不利な特徴を持つ「睡眠」が、進化の中で淘汰されず、現代の私たちまで受け継がれました。つまり意識がなくなるという圧倒的不利を背負ってでも、「睡眠」という行為は人間に不可欠だった、ということなのです。なので、我々人間にとって、どうやら「睡眠」が真に不可欠なもの、というのが現在の睡眠科学の結論になっています。
「今日は忙しいから睡眠時間を削ろう」ではなく、「睡眠時間は確保する。その中でどうやりくりするか」という発想に転換することが、根本的な解決への第一歩です。
質より量、完璧より継続
繰り返しになりますが、睡眠時間確保において大切なのは「質より量」「完璧より継続」です。
毎日同じ時間に寝られなくても、週の大半で必要な睡眠時間を確保できていれば上々です。寝具や睡眠環境が完璧でなくても、まずは時間の確保から始めましょう。
小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな変化をもたらします。まずは「睡眠時間の量を最優先で確保する」という原則を胸に、次節の具体的な睡眠時間の確保方法に進んでください。
逆算時間設計術
ここからは、睡眠時間確保のための具体的な時間設計に入っていきます。逆算時間設計術は、自分で決めた就寝時間から逆算して、1日の「固定時間」を設計していく手法です。
逆算時間設計術では「睡眠時間を確保する」ところからスタートして、1日を遡りながら残りの時間でやることを順次固定時間として決めていきます。
分かりやすさのために、以下のような背景の社会人を例に、具体的な時間設計を考えていきます。
- 30代社会人
- 配偶者あり、小学生の子ども1人
- 平日は残業あり、21-22時帰宅が常態化
- 土日も家族との時間や家事で忙しい
- 資格取得や副業にも取り組みたいと考えている
自身の状況と異なる部分は、差し引いたり付け加えたりして、自身の生活に置き換えて読み進めていただければと思います。
Step1:就寝時間を決定する
あなたの必要睡眠時間から就寝時間を設定
まず、前節で確認した「あなたが機能するために必要な最低限の睡眠時間」を基に、就寝時間を決めていきます。
例えば、毎朝6時30分に起床する必要があり、あなたに必要な睡眠時間が7時間なら、就寝時間は23時30分となります。8時間必要なら22時30分が就寝時間です。
この計算は単純ですが、重要なのは「起床時間に合わせて就寝時間を決める」という順序です。
平日と休日の基本パターンを決める
平日と休日で起床時間が大きく異なる場合は、それぞれの就寝時間を設定します。ただし、あまりに大きな差は避けて、できる限り一定のリズムを保つようにしてください。
- 平日:6時30分起床、23時30分就寝(7時間睡眠)
- 休日:8時起床、25時就寝(7時間睡眠)
睡眠時間の量は一定に保ちながら、生活リズムに合わせて時間帯を調整します。
Step2:就寝準備時間を逆算して固定する
就寝前に必要な時間を洗い出す
就寝時間が決まったら、次は就寝前に必要な時間を逆算します。
この例では、就寝前に合計90分(1.5時間)必要となります。
就寝準備開始時間を固定する
23時30分に就寝するなら、90分前の22時が「就寝準備開始時間」となります。この時間になったら、就寝準備に入る。これを固定時間として設定します。
就寝準備開始時間は、あなたの1日の中で「動かない境界線」です。この時間になったら気持ちよく眠ることに向けて動き出します。
Step3:帰宅から夕食終了までの時間を逆算して固定する
就寝準備前に必要な時間を設定する
就寝準備開始時間が決まったところで、さらに遡って、22時の就寝準備開始前、帰宅から夕食終了まで必要な時間を設定します。
例では、合計60分(1時間)が必要です。
帰宅時間リミットを算出する
22時の就寝準備開始前に60分必要なら、21時が「帰宅時間リミット」となります。
設計完了
この逆算時間設計で、23時30分就寝(7時間睡眠)を実現するためには21時までに帰宅する必要があることが分かりました。
現在の帰宅時間が21-22時なら、0-60分早く帰宅する必要があります。この時間短縮が、睡眠時間確保のための具体的な目標となります。
8時間睡眠のため、もし22時30分就寝を目指すなら、以下のようになります。
この場合、現在の帰宅時間から60-120分(1-2時間)早く帰宅する必要があります。
ちなみに、冬の朝が寒くて辛いという方は、以下の記事もぜひお読みください。
逆算スケジュールの実行方法
ここからは、逆算時間設計術で決めた、睡眠時間確保のための逆算スケジュールを、実際の生活で機能させるための方法について解説していきます。
逆算時間設計術で固定時間を設計しただけでは、まだ絵に描いた餅。設計したスケジュールと現状とのギャップを把握して、そのギャップを縮めていく具体的なアプローチが必要です。
現状把握
まずは、あなたが設計した固定時間と現実の行動がどれくらい乖離しているかを正確に把握しましょう。
前提:自分を責める意図は一切必要ない
まず初めに伝えておきたいのは、これから行なっていく現状の確認を通して、自分を責める意図は一切必要ないということです。
現状を把握するのは、睡眠時間を確保している未来の自分に向かって、どんな問題が今あるのか、「ありたい自分」と「今の自分」の間にどれくらいの距離があるのかを掴むためでもあります。
現状を確認して、(自分はこんなにダメ)と、自分の出来なさを認識する自己批判の種とするではなく、ありたい状態に向かう出発点をナビに入れる行為と捉えて、やっていきましょう。
1. 実際の帰宅時間を記録
逆算スケジュールで設計した帰宅時間に対して、実際の帰宅時間がどうなっているかを1週間記録してください。
平均してどれくらいプラスになっているか、曜日による違いはあるか見えてきます。
2. 就寝準備開始時間のチェック
就寝準備開始時間についてもチェックします。
1.の帰宅時間記録と合わせて、準備時間の押しが就寝時間にどう影響しているか、現状が分かります。
3. 帰宅を困難にしている要因の特定
帰宅が遅れる要因を具体的に分析します。
要因を特定することで、改良の余地があるポイント候補が見つかりやすくなります。
4. 帰宅後時間の現状を言語化
帰宅した後、実際に何をしてどう時間を使っているかを詳細に記録します。
記録に残すことで、後から振り返って工夫できる部分はないか、探すための手がかりを残せます。
5. 現在の帰宅時間と目標のギャップを数値化する
1週間の記録から、平均的なギャップを数値で把握します。
数値化により、目標までの距離が明確になります。継続して記録をつけていくことで、目標に近づいていく成長の確認指標としても活用可です。
ギャップ縮小
続いて、現状把握で特定した「帰宅を困難にしている要因」に対して、具体的なアプローチ方法を検討していきます。
上司・同僚が残っているため帰りづらい雰囲気への対処
多くの職場で見られる「周りが残っているから帰りづらい」という雰囲気は、個人の意識だけでは解決困難な構造的問題です。しかし、工夫次第で状況を改善することは可能です。
最も重要なのは、課題の分離という考え方です。
自身の業務が完了しているのであれば、その後のあなたの行動を他者がどう思うかは他者の課題なのです。あなたの課題ではありません。
他者からの印象を決めることはできないのです。究極的な話、あなたがどれだけ他者に気を遣って過ごしていても、あなたを嫌う人は存在し得ます。
また、「同僚がまだ残っているから手伝わなければ」と感じるかもしれませんが、過度に手伝いすぎることは、実は同僚の成長を妨げる要因になる可能性もあります。
なので、罪悪感を持つ必要はありません。あなたが定時で帰ることで、職場全体の働き方改善の先例を作ることにもなります。
とはいえ、だからといって他者に傍若無人に振る舞うのは話が別です。自分を犠牲にしない気遣いはした方が良いでしょう。
「課題の分離」と同時に、退勤理由の明確化と事前連絡も効果的です。単に「お疲れさまでした」と言って帰るのではなく、「子どもの迎えがあるので失礼します」「通院のため定時で失礼します」など、具体的な理由を伝えるようにします。理由が明確であれば、周囲も受け入れやすいでしょう。
朝一番に上司に「今日は○時に退社させていただきます」と事前に伝えておけば、夕方になっていきなり帰るというような印象は避けられます。自分の業務の進捗状況と翌日の予定も併せて報告すれば、双方とも安心した状態で退勤できます。
定時間際に新しい仕事を振られることへの対処
定時直前に急な仕事を依頼されるのは、多くの人が経験する問題でしょう。
最も手っ取り早いのは、16時頃を目安に上司と積極的にコミュニケーションを取ることです。「本日の業務は◯時頃に完了予定です。新しい案件はございますか?」と自分から確認を取れば、定時間際の急な依頼を防ぎやすくなります。職場によっては、上司も「そういえば」と思い出して依頼するケースが結構あるので、早めの確認で予防できます。
依頼された場合の確認と交渉も重要です。「分かりました」と単に引き受ける代わりに、「こちらの作業時間は約○時間を見込んでいますが、本日中でしょうか?それとも明日の朝一でも大丈夫でしょうか?」と確認します。
本当に緊急性が高い案件の場合は、翌朝対応を提案します。「明日7時30分に出社して対応し、9時には完了させます」と、夜遅くまで残業するよりも効率的で、かつ睡眠時間を確保できる折衷案を提示できます。
会議が長引く・遅い時間に設定されることへの対処
会議時間の管理は個人では難しい問題ですが、工夫できる点がなくはないです。
最も効果的なのは、会議の目的と終了時間の確認です。会議が始まったら「本日の会議は◯時終了予定でよろしいでしょうか?」と確認して、同時に会議の目的も明確に確認しておきます。何を決める会議か、そして会議のケツを明確に共有することで、終わりを見て議論しやすくなるため、全体の時間短縮にもつながります。
もう1つ重要なのは、会議への能動的な働きかけです。受動的に静観していては、他者のペースで他者が「終わり」と言うまで終わりません。「この議題については結論が出たので、次に進めるのはいかがでしょうか」「まずは、重要度の高いこの議題からいかがでしょうか」など、進行に積極的に関与する働きかけがあった方が、会議時間を短縮につながりやすいです。(もちろん、自分の今できる範囲で。)
そのためには、会議前の情報収集が不可欠です。議題について事前に情報を集め、論点を整理し、自分なりの意見や提案の準備が、会議を建設的にし、議論を効率的に進められます。
繰り返し作業の自動化
毎日または定期的に行う作業は自動化を選択肢に入れてください。大幅な時間短縮が可能です。最初の設定に時間はかかりますが、一度設定すれば、それ以降永久に時間を節約してくれます。
例えば、会議議事録の文字起こしは、音声認識ソフトやAI議事録サービスで自動化できます。会議中に録音し、自動で文字起こしされたものを後で編集するだけで、ゼロから議事録を作成するよりもだいぶ楽になります。1回の会議で30-60分の時間短縮が可能で、週に複数回会議がある場合は、週2-3時間の節約になります。
メール定型文のテンプレート化も効果的です。よく使う挨拶文、お礼メール、確認メール、謝罪メールなどをテンプレート化して、ワンクリックで呼び出せるようにします。1通あたり2-3分の短縮でも、1日10通メールを書けば20-30分の時間短縮になります。時間短縮だけでなく何通も同じものを書く単純作業が楽になるのは、心理的にも負担を軽くしてくれます。
経費精算の自動化では、レシート撮影で自動仕訳できるアプリを使用します。月末にまとめて行う経費精算作業(通常1-2時間)を、日々の撮影だけで完了させることができ、大幅な時間短縮と精神的負担の軽減が可能です。
日常生活の場面にも自動化を検討できる繰り返し作業があります。
家事の自動化は最も効果の大きい領域です。食洗機があれば食器洗いの時間(1日15-20分)が皿を入れる5分程度になり、洗濯乾燥機なら洗濯物を干したり取り込んだりする時間(1日10-15分)が不要になります。掃除ロボットを平日の外出中に稼働させておけば、掃除機をかける時間も削減できます。合計すると、週3-5時間の時間確保が可能です。
食材や日用品の買い物も意外と時間がかかります。ネットスーパーの定期注文を活用すると、買い物時間(週2-3時間)を大幅に削減できます。よく購入する商品を定期注文に回して、必要に応じて追加で買い物に出かけるようにすれば、「何を買うか考える時間」も短縮できます。
これら自動化を段階的に導入することで、週単位で5-10時間の時間確保が可能になります。帰宅時間の実現、巡って睡眠時間確保に大きく近づくことができます。
以上、睡眠時間を削る現状から、睡眠時間をちゃんと確保できてる状態までのギャップを埋める方法を紹介しました。
これらのギャップ縮小策は一気にやろうとせず、段階的に進めることが重要です。
まずは「平均帰宅時間を10分早める」ことから始めて、それが習慣化したら「さらに10分早める」という具合に、少しずつ帰宅リミットに近づけていきます。
劇的な変化を求めず、段階的な改良を積み重ねることで、睡眠時間を確保できる生活リズムが現実に見えてきます。
挫折しないために知っておいてほしいこと
ここからは、時間に追われる毎日でも睡眠時間を確保できる、より良い自分に持続的に変容していく中で、「挫折しないために知っておいてほしいこと」を2つお伝えしていきます。
1. 失敗はなく、今まで通りと成功しかないこと
出来なかった日は「失敗」ではない
設定した時間に就寝準備を始められなかった日、予定より遅く寝てしまった日は「失敗」ではありません。それは単に「今まで通り」のパターンが出ただけです。
「失敗」という言葉には自分を責める気持ちが込められていますが、出来なかったのは失敗ではなく今まで通りなんです。今やろうとしている工夫では成功しなかっただけ。だから、自分を責める必要は全くありません。
少しでも前進があった日は「成功」
一方で、設定時間より少し早く準備を始められた日、計画通りにタスクを終えられた日は、間違いなく「成功」です。目標に完全に到達していなくても、前進があればそれは成功です。
- 目標より10分遅れたが、昨日より5分早くできた → 成功
- 固定時間を30分オーバーしたが、昨日より1時間短縮できた → 成功
- 週7日中3日だけ計画通りにできた → 成功
成功の定義を「前進」としてください。0.1歩でも、0歩とは雲泥の差があります。
今まで通りの日があっても問題ない
今まで通りのパターンに戻ってしまう日があっても、それは全く問題ありません。人間である以上、体調不良や急な予定変更、精神的な疲れなどで、いつも通りの行動に戻ることは自然なことです。
大事なのは、「今まで通りの日があっても、明日また前進すればいいだけ」という捉え方。一度戻ったからといって、これまでの努力が無駄になるわけではありません。どんな日でも、あなたの後ろには積み重ねてきた行動があります。
2. どんなに小さなことでも「出来たこと」と「出来た自分」を褒めること
たとえどんなに小さなことでも、出来たこと、そして出来た自分を褒めてください。過剰なくらいがちょうどいいです。
「出来たこと」と「出来た自分」を褒める理由
人間の脳は「できていないこと」に注目する傾向があります。「今日も目標時間に帰宅できなかった」「目標に程遠い自分はダメ」といったマイナス面ばかりに意識が向くことを、継続するのはかなり難しいです。
脳科学的な側面から言うと、褒められることは脳内でドーパミンの分泌を促し、脳はその行動を良い行動と判断します。そして良いと判断した行動は、同じ行動を取ろうとするハードルが下がることが分かっています。
つまり、自分を褒めることは、良い行動を続けやすくするのです。
小さな変化でも「できた」という成功体験を積み重ねることで、脳は「この行動は良いことだ」と学習し、継続しやすくなります。
「昨日より5分早く帰宅できた」「今週は先週より1日多く、計画通りに就寝準備を始められた」のような小さな変化を褒めることが、進歩の積み重ねだけでなく、次の行動も取りやすくしてくれます。
変化のプロセス自体を楽しむ
そして、完璧な目標達成よりも、変化を起こしている自分自身を評価して、そのプロセスを楽しんでください。
「今週は3日成功した。先週は1日しか成功しなかったから、確実に前進している」というように、数週間単位で自分の変化を観察、成長を認識してください。
成果が出るまでの時間は人それぞれですが、変化に向かう姿勢は即座に評価できます。毎日少しずつでも前進していること、新しいことに挑戦していること、これらすべてが褒めるべき要素です。
周囲からの評価ではなく、自分が決めたルールを守れた自分を評価する
家族から『最近元気になったね』と言われるなど、周囲からの評価も嬉しいものですが、同じように大切なのは「自分が決めた小さなルールを守れた自分」を評価することです。
他者は劇的な変化にしか気づかないかもしれませんが、あなたは自分の小さな努力と変化をすべて知っています。「今日は10分早く就寝準備を始められた」「早く退勤するための工夫を1つ試せた」といった、他人には見えない小さな成功も、すべて価値ある変化です。そしてその価値を認めてあげるのが、あなたの使命です。
自分が設定した基準で、自分の成長を観察する。そして褒める。これが、長期的な変化を支える最もシンプルなサイクルです。
逆算スケジュールを自分に慣らしていくためのTips
最後に、逆算スケジュールを自分に慣らしていくための実践的なTipsをいくつか紹介していきます。
アラーム設置
固定時間の開始時刻にアラームを設定しましょう。アラームは自分が決めた逆算スケジュールを都度思い出させてくれるきっかけになります。
アラーム名には具体的な行動を入力しておきましょう。
アラームが鳴ったときに、何をすべきかが一目で分かります。音を鳴らしたくない場合は、バイブレーションでもokです。
固有のアラーム音を設定する
アラーム音は、固定時間ごとに変えると効果的です。音を聞いただけで次に何をすべきかが分かるようになります。
こちらもバイブレーションでもok。異なるバイブレーションパターンを当てはめれば効果的です。
守れた固定時間に丸つけ
カレンダーや手帳に、固定時間ごとの達成状況を記録してみましょう。
| 帰宅時間 | 夕食時間 | 就寝時間 | |
| 月曜日 | ◯ | ◯ | |
| 火曜日 | ◯ | ||
| 水曜日 | ◯ | ◯ |
守れた固定時間に「◯」をつけていく過程で、自分の進歩が視覚的に分かります。
ちなみに、守れなかった場所に「×」をつける必要はありません。空欄は今まで通りの意味です。今まで通りと成功の2つしかない記録の方が、小さな成功を実感していけます。
達成率の把握と改良点の発見
達成状況の記録を付けていくと、どの固定時間が守りやすく、どの時間が守りにくいかが明確になります。
「帰宅時間が守れた日は、就寝時間を守れる確率が高い」「帰宅時間は、週末に近づくにつれ守りづらくなってる」など。
この情報を元に、守りにくい固定時間の改良案や工夫を検討できます。
持ち物や環境の事前セット
固定時間になってから「あれはどこだっけ?」「これを準備しなければ」と探し回るのは、時間を食うし何より疲れます。
各固定時間に必要なもの・環境を整えておくことで、スムーズに行動を開始できるようになります。
その他、良い睡眠習慣に関するアイデアについては、以下の記事で解説しています。
まとめ
今回は、時間に追われて毎日睡眠時間が削られてしまう方に向けて、「どうすれば睡眠時間を確保できるのか」を解説しました。
- 睡眠時間を削るメリットよりも、失うデメリットの方が大きい。
- 睡眠時間確保の原則は「量を優先」「最低限必要な睡眠時間を知る」「今の生活にフィット」「削れない時間として扱う」「完璧より継続」。
- 逆算時間設計術で、就寝時間から逆算して1日の固定時間を設計する。
- 現状把握とギャップ縮小で、睡眠時間を確保する流れを実行できる。
- 挫折しないために「今まで通りと成功しかない」「出来た自分を褒める」視点が大切。
私たちは忙しい現実の中で、つい「睡眠を削ればいい」と考えがちです。それは短期的な安堵を得ても、長期的に失うものが大きすぎます。
時間に追われているその最中では、失っているものに気づきづらいのはあります。しかし、大きな問題となって降りかかってから気づくのでは遅いことも事実です。
この記事では、時間に追われる毎日でも、睡眠を削れないものとして時間を逆算的に設計し、持続的に自身の健康を守っていく方法を解説しました。
本記事で紹介した内容を実践すれば、「今日も前進があった」と思える日が増えて、時間に追われる日々でも自分を肯定して過ごせる日が増えていきます。
ぜひ今日から「睡眠時間は削れない」として、逆算スケジュールを小さく試してみてください。少しずつでも続けることが、ありたい自分への入り口となります。
睡眠時間確保の次は、睡眠の質にもこだわりたいという方は、以下の記事もあわせてどうぞ。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。