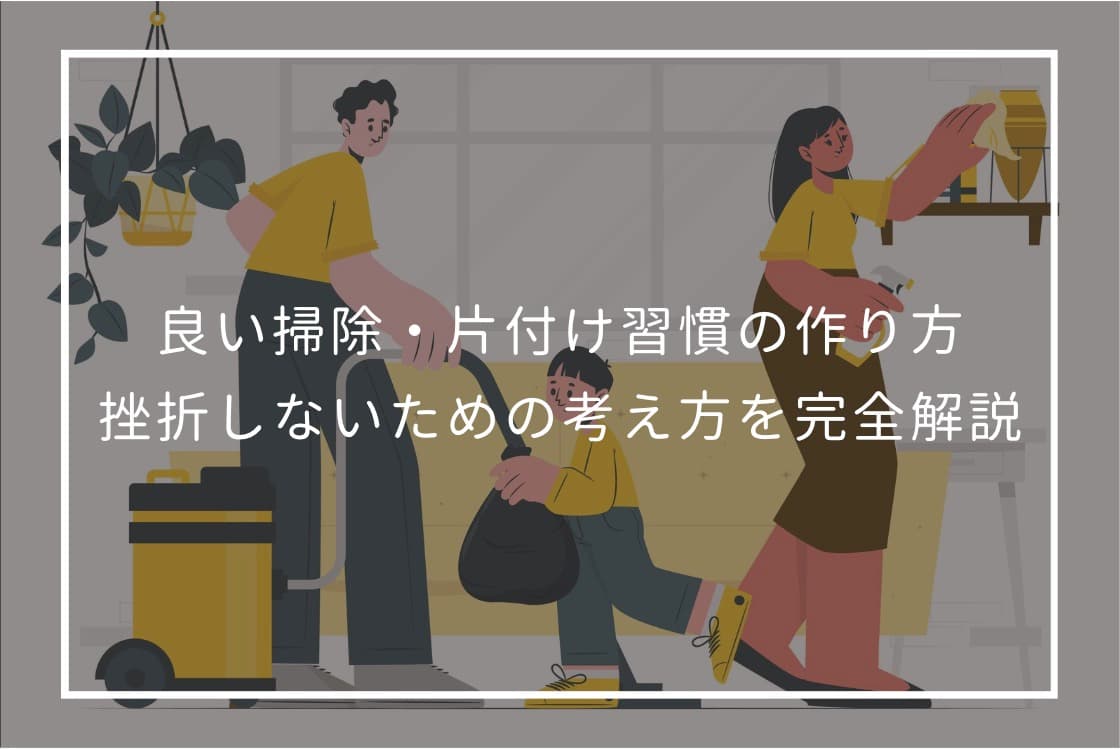こんにちは、けうzenです。
「部屋を楽にキレイにするために掃除・片付けを習慣にしたいけど、結局続かない…そもそも始められない…」こんなお悩みはありませんか?
キレイな部屋を維持したいと思っても、気づけば散らかっていて、また一から片付けるの繰り返し…。そんな状況に疲れてしまうこと、ありますよね。
ということで今回は、続かない原因を克服して、無理のない良い掃除・片付け習慣を身につけていくための方法や考え方のコツを解説していきます。
この記事を読むことで、良い掃除・片付け習慣を作るための必須要素、よくある続かない原因を克服するコツ、効果のある行動や挑戦中の注意点などがまるっと分かります。
「今年こそは散らかった部屋とおさらばしてキレイな部屋で過ごしたい!」という方は、ぜひ最後までお読みください。
それでは、いってみましょう!
良い掃除・片付け習慣とは
掃除・片付けを習慣にできると、単に家をキレイに保てるだけでなく、生活の質そのものも向上します。
しかし、そもそも何をもって良い掃除・片付け習慣と言えるのか、いまいちはっきり分からない方も多いのではないでしょうか。
そこでまず、良い掃除・片付け習慣に必須の3要素について解説していきます。
掃除・片付け手順
良い掃除・片付け習慣には、スムーズに行うための「手順」が必要です。
手順が決まっていないと、どこから手をつければよいのか分からず、結局後回しになってしまいがちで、継続するためのハードルが高くなってしまいます。
たとえば、リビングの掃除なら「ホコリは上から下に落ちるから、高いところから順番に掃除する」といったルールを作っておくと、何も考えずに作業に取り掛かれます。
片付けなら、「使ったものを元の場所に戻す」「まずは目につく範囲のものを片付ける」など、シンプルなルールを決めておくことで、迷いなく行動に移せるようになります。
掃除・片付けの習慣化には、この「考えなくても動ける手順」が必須です。
定期的な時間の確保
良い習慣には、無理なく続けられるペースでの時間の確保があります。
たとえば、「1日1箇所5分だけ掃除する」と決めておけば、短時間で済み、かつ終わりが決まっているので取り組みやすくなります。忙しい日なら、「机の上を拭くだけ」「玄関の靴を揃えるだけ」など、ほんの数秒でできることをやるだけでもOKです。
掃除や片付けを続けるうちに、心理的なハードルが下がり、「やらなきゃいけない面倒なこと」ではなく「自然とやること」へと変わっていきます。定期的な時間の確保は、掃除・片付け習慣を自然と強化してくれます。
恩恵の実感
習慣を定着させるためには、「やることで得られるメリット」を日常で実感できることが重要です。
なぜなら、まだ慣れてない行動を続ける上で、その行動の価値を実感できることは、「こんなに良いことがあった、次もやろう」と継続することを後押ししてくれるからです。
掃除や片付けをすると、単に部屋がキレイになるだけでなく、気持ちもスッキリして前向きに日常を送りやすくなります。また、自分の過ごす空間を快適にすることで、「自分で自分の環境を整えられる」という自己効力感も高まります。
特に、仕事や勉強の集中力を上げたい人にとっては、整理整頓された空間が大きな助けになります。散らかった部屋では気が散りやすくなりがちですが、スッキリした環境なら余計なストレスが減り、やるべきことに集中しやすくなります。
「掃除・片付けをすることで、自分にどんな良い影響があるのか」と、掃除・片付けの恩恵を意識することが、習慣の意義を自然と実感させてくれます。
良い掃除・片付け習慣で得られるもの
良い掃除・片付け習慣を身につけることは、日常生活にさまざまなメリットをもたらします。
ただ部屋がキレイになるだけでなく、時間やお金の節約、心の安定にもつながるのが大きなポイントです。ここからは、具体的にどんな良いことがあるのかを解説していきます。
清潔
まず、なんといっても部屋がキレイになります。机の上にホコリが溜まらなくなります。壁やモノの汚れが減ります。
衛生的な環境が整うため、快適度が格段に向上します。また、キレイな空間は心理的なリフレッシュにもつながり、ストレスを減らす効果も期待できます。
特に寝室やリビングなど、長時間過ごす場所が清潔だと、日々の満足感が高まるでしょう。
探しものが減る
探しものをする時間が大幅に減ります。特に、忙しい朝や外出前に「あれどこだっけ?」とバタバタすることがなくなるのは大きなメリットです。
さらに、失くし物自体も減るため、余計なストレスを感じずに済みます。探しものがなくなることで、時間にも気持ちにも余裕が生まれます。
空間の余裕
部屋の中に「流動的なスペース」が増えます。
床やテーブルの上がスッキリすることで、空間に余裕が生まれ、開放感が得られます。部屋全体の圧迫感が減り、体を動かしたり、ストレッチしたり、ゆったり過ごす環境を作りやすくなります。
特に狭い部屋ほど、片付けの効果は実感しやすいでしょう。
節約
掃除・片付け習慣は、意外とお金の節約にもつながります。
まず、物を大切に扱うようになるため、買い替えの頻度が減り、無駄な出費が抑えられます。また、持ち物を把握しやすくなることで、「同じものをうっかり買ってしまう」というミスも防げます。
さらに、せっかくだから整理整頓された状態を維持しようという意識は、本当に必要な物だけを厳選することにつながってきます。
自己管理能力の向上
時間の使い方やタスク管理能力が自然と向上します。
限られた時間の中で効率よく掃除をする習慣がつくと、他の生活習慣や仕事にも良い影響を与えます。
また、自分の空間を整えることが「自分をコントロールできている」と、自己肯定感も自然と向上していきます。
掃除・片付け習慣が続かない理由
掃除や片付けを習慣にしようとしても、なかなか続かないことはよくあります。最初はやる気があっても、気づけば元の散らかった状態に戻ってしまった…という経験がある人も多いのではないでしょうか?
掃除・片付けが続かない理由には、「モチベーション、能力、きっかけ」の3つの側面が関係しています。なぜ習慣にならないのかを理解することで、挫折を防ぎ、続けるための工夫が見えてきます。
モチベーションに関連する理由
ゴールが曖昧
掃除や片付けを「なんとなくやらなきゃ」と思っていても、目的やゴールがはっきりしていないと、やる気が起きにくいものです。
例えば、「部屋を綺麗にしたい」と漠然と考えているだけでは、どこまでやれば満足なのかが分からず、途中で疲れてしまいます。
また、ゴールが曖昧なままだと成果を実感しにくく、「せっかく掃除したのに達成感がない」と感じてしまいがちです。
すぐ散らかる、意味ないと感じてしまう
せっかく掃除や片付けをしても、すぐにまた散らかってしまうと、「やる意味がない」と感じることがあります。特に家族や同居人が片付けをしない場合、「自分だけ頑張っても無駄だ」と、やる気が失われがちです。
いくら掃除してもキレイな状態を保てないなら、いっそ散らかったままでいいと感じてしまいます。
完璧主義
「完璧に掃除しないと意味がない」と考えてしまうと、掃除・片付けのハードルが上がりすぎてしまいます。
「部屋をピカピカにしなきゃ」「全部一気に片付けなきゃ」と思うほど、行動を始めるのが億劫になり、結果としてやらなくなってしまうことも。
少しの汚れも許さない、と考えてしまうと掃除のプレッシャーが高まり動き出しづらくなってしまいます。
能力に関連する理由
時間がない、後回しになる
忙しい毎日の中で、掃除や片付けはどうしても後回しになりがちです。「時間ができたらやろう」と思っているうちに、気づけば何日も経っていた…なんてこともよくあります。
また、「掃除にはまとまった時間が必要」と、掃除のハードルが高くなっているかもしれません。
掃除場所を決められない
「どこから手をつければいいのかわからない」と悩んでしまうことも、掃除習慣が続かない原因になります。
掃除を始める前に、どこを掃除するか決めるところから始まってしまうので、手順が1つ増え、心理的ハードルが高まってしまいます。
道具がない
掃除道具が手元になかったり、片付けるための収納が整っていなかったりすると、「掃除しよう!」と思っても、すぐに取り掛かれません。
例えば、「掃除機を出すのが面倒」「掃除に必要な道具がない」「収納スペースが足りなくて片付けられない」など、掃除・片付けのハードルが上がってしまいます。
きっかけに関連する理由
自分の記憶頼り
掃除・片付けを「やらなきゃ」と思っていても、日々の忙しさの中でつい忘れてしまうことがあります。
「思い出したときにやろう」と自分の記憶頼りにしていると、他のことに気を取られて、掃除することが記憶の彼方にすっかり消えてることもあるのではないでしょうか。
始め方が曖昧
「掃除しよう!」と思っても、具体的に何から始めればいいのか分からず、結局手をつけられなかったという経験はないでしょうか。
手始めの行動が曖昧だと、無意識に「難しい・面倒」と感じ、せっかく掃除に向いた意識が行動につながらず仕舞いなことが往々にしてあります。
例外への対処がない
「忙しい」「今日は疲れてるから…」といった理由で、決めてたことをサボることは誰にでもあります。しかし、この例外への対処を決めておかないと、そのまま掃除習慣が途切れてしまうことがあります。
特に「毎日完璧にやらなきゃ」と思いすぎると、少しでもできなかったときに挫折しやすくなります。
***
掃除や片付けが続かないのには、理由があります。しかし、それぞれに対策を立てることで、習慣化することは可能です。
良い掃除・片付け習慣の作り方
掃除や片付けを習慣化できると、部屋が常にスッキリして気持ちよく過ごせるだけでなく、「やらなきゃ…」というストレスからも解放されます。
ただ、「やろう!」と意気込んでも続かないことが多いのが現実。そこで、無理なく掃除・片付けを習慣化するために、ここからはモチベーション、能力、きっかけの3つの視点から工夫する方法を紹介していきます。
モチベーションの工夫
願望を明確にする
なんとなく掃除を頑張ろうとしても、気が乗らなかったり、すぐ挫折したりしがち。まずは、「なぜ掃除・片付けを習慣化したいのか?」をはっきりさせましょう。
例えば、
- 散らかった部屋にストレスを感じたくない
- スッキリした部屋でゆっくりくつろぎたい
- 積んでたものに体が触れて盛大に崩れ散らかって、虚無な気持ちにもうなりたくない
具体的な理想の状態を考えると、「掃除する意味」が自分の中ではっきりしてモチベーションにつながります。紙に書き出したり、言葉にしたりするのも良いでしょう。自分の願望をより意識しやすくなります。
キレイでうれしいポイントをイメージする
掃除・片付けをした後の恩恵に意識を向けてみましょう。今の行動がどんな良い未来につながっているかイメージできるほど、行動の意義を認識して動き出しやすくなります。キレイで片付いた部屋で自分は何をしているでしょうか?
- 朝、スッキリ片付いた部屋で優雅にコーヒーを飲んでる
- 整った環境で仕事に集中できてる
- いつ人が来ても慌てて片付けなくていい
具体的な場面を思い描くことで、「掃除=気持ちいい未来へのステップ」と考えられるようになり、モチベーションがアップします。小さな成功体験を積み重ねて、「掃除すると気分がいい」と実感するのも効果的です。
60点でよしとする
まずは60点を目標にしてみましょう。完璧を求めすぎると、「全部きれいにしなきゃ!」とプレッシャーで逆にやる気をなくしてしまいます。最初はほどほどでOKです。70点、80点と上げていくのは慣れてからでも遅くないです。
具体的には、
- とりあえず見た目がマシになればOK
- 今日はここだけで十分
- できなかった部分より、できた部分に目を向ける
「完璧じゃなくてもいい」と思えると、掃除へのハードルが下がり、続けやすくなりますよ。
能力の工夫
1分でできる掃除をつくる
「掃除=大掛かりな作業」と思うと、つい後回しにしがち。そこで、「1分でできる掃除」を用意して、気軽に取り組めるようにしましょう。
例えば、
- 机の上を拭く
- 玄関の靴を揃える
- キッチンのカウンターを整理する
「たった1分なら」とハードルを下げておくと、自然と掃除・片付けしやすくなります。
1回1箇所に場所を決める
一気に部屋全体を片付けようとすると、終わりが見えなさすぎて結局やる気にならないことも。そこで、「今日はここだけ」と小さく区切って場所を決めてしまいましょう。
具体的には、
- 今日は机の上だけ片付ける
- クローゼットの一段目だけ整理する
- ソファ周りだけ整える
範囲を狭めると考えることが減って、着実に掃除・片付けを実行しやすくなります。また、「できた!」と達成感を得やすくなり、自然と習慣にしやすくできます。
きっかけの工夫
道具・手順を決める
掃除をするのが面倒に感じる原因の一つは、「何をどうすればいいか考えるのが面倒」という点。なので、掃除・片付けの道具や手順をあらかじめ決めておきましょう。スムーズに取りかかれるようになります。
例えば、
- 道具の配置を工夫する
- リビングにはウェットシートを常備
- 玄関にホウキを置く
- キッチンに小さいゴミ袋をストック
- 手順をルーチン化する
- 朝起きたらテーブルを拭く
- 夜寝る前に床のものを片付ける
「掃除=特別な作業」ではなく、「毎日のちょっとした動作」と捉えて日常に取り入れることで、朝の歯磨きや夜のお風呂と同じようにいつものルーティンとして無理なく続けられるようになります。
効果のある行動紹介
ここからは、掃除・片付け習慣を身につける上で、効果のある行動の工夫を4つ紹介していきます。
モノの住所決め
片付けがうまくいかない理由の一つが、「モノの定位置が決まっていない」ことです。置き場所を適当にしていると、使った後にどこに戻せばいいか分からなくなり、ついその辺に置いてしまいがち。そこで、モノに『住所』を決めることで、散らかりにくい環境を作れます。
- リモコンはテーブルの左端
- 鍵は玄関のカゴ
- スマホ充電器はベッド横のコンセントに固定
モノに明確な定位置を決めることで、「使ったら戻す」ルールが明確になって、片付けの手間が減ります。
片付けが苦手な人ほど、定位置をラベリングしたり、写真を撮ったりするとさらに効果的です。「ここに置く」と視覚的に分かると、迷わず片付けができるようになります。
予約
自動化できることはあらかじめ予約してしまいましょう。最近は洗濯機やルンバなどの掃除ロボットなど予約機能があるものが多いので、機能を活用して自動化してしまうのが便利です。そしてその予約時間に合わせて必要な行動も予約してしまうのです。
例えば、
- 予約時間に洗濯機が回り終わるように〇〇時までに洗うものを入れておく
- ルンバなど掃除ロボットが掃除できるように〇〇時までに床に置いてるものを片付ける
自動で動き出す時間に合わせて自分がする必要がある行動も予約しておくと、ルーティンにしやすいです。
家電の予約機能を駆使して自分の行動も合わせて予約していまいましょう。
スイッチングアクション
「掃除しよう!」と思っても、なかなか動き出せないことはありませんか? そんなときは、「〇〇をしたら掃除を始める」という風に、掃除をいつもする行動の後にくっつけると、スムーズに行動できます。これをスイッチングアクションと呼びます。
例えば、次のようなルールを決めておくと、無意識に掃除や片付けができるようになります。
- コーヒーを淹れたらキッチン周りを拭く
- 帰宅したらバッグの中を整理する
- 歯を磨いたら洗面台を拭く
上の例では、スイッチングアクションは「コーヒーを淹れる」「帰宅する」「歯を磨く」にあたります。
掃除を「やるかやらないか考える時間」がなくなり、決まった流れで動けるのがポイント。
さらに、このルールを繰り返すことで、脳が「〇〇をしたら掃除する」というパターンを覚え、自動的に体が動くようになります。やる気に頼らずに掃除ができるので、習慣化しやすくなります。
真珠の習慣
「掃除って面倒…」と感じるのは、当たり前のこと。だからこそ、掃除を楽しくする工夫を取り入れるのが大事です。
「めんどい…」「だるい…」と感じた瞬間を、掃除・片付けしやすくなる行動のきっかけにしてしまいましょう。これを「真珠の習慣」と呼びます。ネガティブを感じる瞬間に「楽しいこと」をセットして、行動しやすくする方法です。
例えば、以下のような設計です。
- 皿洗いが面倒と感じた瞬間に、お気に入りの音楽をかけて、皿洗いし始める。
- 掃除機をかけるのが面倒と感じた瞬間に、掃除後のスッキリした部屋を一度イメージして、掃除機をかけ始める。
- 片付けをやりたくないと感じた瞬間に、終わった後にコーヒーを飲む楽しみを思い浮かべて、片付け始める。
「掃除=嫌なこと」ではなく、「掃除をすると楽しいことがある」と脳に覚えさせることで、苦手意識を薄めていけます。
「面倒だな」と思った瞬間に、楽しいと感じる行動をつなげて、掃除・片付けを始める合図にするのがおすすめです。
便利アイテム
片付けや掃除を習慣化するには、「やる気」だけに頼るのではなく、便利なアイテムを活用して楽に続けられる仕組みを作ることが大切です。ここからは、掃除・片付け習慣をサポートする便利なアプリやデバイスを紹介していきます。
CAJICO(家事アプリ)
「掃除の予定を決めるのが面倒」「気づいたら家が散らかっている」 という人におすすめなのが、家事管理アプリ「CAJICO」です。
このアプリを使えば、掃除や片付けのタスクをリスト化して、「何をいつやるべきか」が明確にできます。

掃除を後回しにしがちな人や、家族で家事を分担したい人にぴったりのアプリです。
Perfect BA(ビフォーアフター)
掃除や片付けを頑張ったのに、「成果を実感できない」「気づいたらまた散らかってしまう」 そんな人におすすめなのが、「Perfect BA」。
Perfect BAは、掃除前と後の写真を記録できるので、自分の頑張りを「見える化」できます。
部屋が散らかると、「どこから手をつければいいのか分からない…」と感じることもありますが、「Before(片付ける前)」の写真を見れば、どこを改善すればいいか一目瞭然。また、「After(片付けた後)」を見返すことで、片付けのモチベーションを維持しやすくなるのもポイントです。
Echo Show(スマートスピーカー)
掃除や片付けを「もっと楽しく」「手間なく」続けたいなら、スマートスピーカー「Echo Show」が便利です。音声操作ができるので、「掃除を始めるきっかけ作り」や「片付けの効率アップ」に活用できます。

「掃除を始めるのが億劫」「やる気が出ない」と感じるときでも、Echo Showを駆使して自然に片付けの流れが作ることができます。
***
片付けや掃除を習慣化するには、「やらなきゃ…」と気合いで頑張るよりも、便利なアイテムを活用してラクにすることが大切です。
- タスク管理が苦手なら「CAJICO」で掃除の予定を見える化
- 成果を実感したいなら「Perfect BA」でビフォーアフターを記録
- 楽しく習慣化したいなら「Echo Show」で片付けをサポート
どれも手軽に始められるので、自分に合いそうなものを試してみてください!
成果の実感方法
掃除・片付けを習慣にするには、「やってよかった!」と実感を得ることが重要です。ただ片付けるだけでなく、その成果を目に見える形で残したり、気分の変化を記録することで、達成感を感じやすくなり、「次もやろう!」と継続しやすくなります。
ここからは、そんな掃除や片付けの成果をしっかり実感するための方法を紹介していきます。
ビフォーアフター
片付けの効果を一目で実感するなら、ビフォーアフターの写真を撮るのが手軽です。
- 掃除・片付けの前後で写真を撮ることで、「どれだけ変わったか」が目で見てわかる。
- 見比べることで「やってよかった!」という達成感を得やすくなる。
- 片付けた状態の写真を保存しておけば、「この状態をキープしよう!」という意識が生まれる。
- 定期的に記録すると、自分の習慣の積み重ねを振り返ることができ、継続のモチベーションにつながる。
スマホのアルバムに「片付け記録」フォルダを作っておけば、後から見返して成長を実感することも可能。特に「どこから片付ければいいかわからない…」というときにビフォー写真を撮ると、進捗がわかりやすくなります。
比較画像を作成するときは、便利アイテムで紹介したPerfect BA[アプリリンク]を使えば簡単です。
メリットを感じた瞬間を記録
片付けたことが「生活の快適さにつながった瞬間」を記録しておくのも、やる気を維持するポイントです。
- スッキリした部屋はやっぱり開放感がすごい!
- 探し物がすぐに見つかった!
- 何となく気分がいい!
感情の変化や気づきをメモしておくと、次の掃除でも同じ良い気持ちを期待でき、モチベーションが高まります。
また、片付けによって「時間が生まれた」「気分がスッキリした」瞬間を振り返ると、「やっぱり片付けてよかった!」と実感しやすくなります。
例えば、ノートやスマホのメモ「片付けてよかったこと」を書き残していくのもおすすめ。具体的なエピソードを書き留めることで、「片付け=自分にとってメリットがあること」と脳が認識し、習慣として定着しやすくなります。
完了アロマ
掃除や片付けの「成果」を五感で楽しむのも、習慣化の方法の一つです。掃除・片付けを終えたら、お気に入りのアロマを焚いて、心地よい香りの中リラックスするのも良いでしょう。匂いに結びついた記憶は強く残るため、「掃除の後=いい香り=気持ちいい」と、スッキリした空間と匂いが脳で結びつきます。
これは「プルースト効果」といわれ、特定の香りや味を嗅いだり味わったりすることで、過去の記憶や感情が呼び起こされる現象が元になっています。
「掃除の後のご褒美」としてアロマを活用すると、心地よい香りとともに片付けた空間の快適さを実感しやすくなるため、成果の実感方法としておすすめです。
挑戦中の注意点
掃除・片付けを習慣化しようとしていると、最初はやる気があっても、途中で挫折しそうになる瞬間が必ず訪れます。 そんなときに「もういいや…」と投げ出してしまわないよう、ここからは掃除・片付け習慣中の注意すべきポイントを紹介していきます。
疲れてるとき
疲れている日は、無理に掃除を頑張ろうとしないのが大切です。
- 体力・気力がない日は、最小限の掃除だけでOK。(ゴミを1つだけ捨てる、テーブルを拭くなど)
- 判断力が鈍っているときに大がかりな片付けをすると、余計に散らかるリスクもある。
- 「0.1でもゼロよりマシ」の意識で、何でもいいからとにかく途切れさせないことが大事。
疲れた日は、「ゴミを1つ捨てるだけ」「床に落ちたものを1つ拾うだけ」など、ほんの少しの行動でもOKです。 「何もしないよりマシ」程度のことでもOKなので、ほんの少しでも何かすることで、習慣を明日につなげられます。
スタートダッシュの罠
最初に張り切りすぎると、続きません。 ゆるく始めるが吉です。
- 「よし、徹底的に片付けるぞ!」と意気込んで、いきなり数時間かけて片付ける → 燃え尽きる。
- 「今日は引き出し1つだけ」「まずは10分だけ」など、小さく始める方が長続きする。
- 一気にやるより、 短時間で終わる方が「またやろう」と思える。
- 最初に完璧を目指さず、「今よりちょっとマシ」を積み重ねると、無理なく続けられる。
やる気があると、一気に全部片付けたくなりますが、それだと続きません。「ちょっとだけでもOK」の気持ちで、無理なく続けることを優先していきましょう。
比較は昨日の自分と
SNSや他人の家と比べる必要はありません。大事なのは今いる場所じゃなくて、前に進んでいくことです。成長は、自分を基準に見ていきましょう。
- 「昨日の自分の部屋」と比べて良くなったポイントを探すと、小さな進歩を実感しやすい。
- 「少しでもやった自分」をほめる習慣をつけると、楽しく続けられる。
- 比べるなら、1週間前・1ヶ月前の自分の部屋! ビフォーアフターの写真を撮るのも効果的。
他人と比べるのではなく、「昨日よりちょっとでも片付けた自分」をほめることが大事です。 その積み重ねが、部屋をきれいにし、自己肯定感の源になっていきます。
成功のハードルを極限まで下げる
「これならできる!」と思えるくらい、ハードルを下げて続けることが大切です。
- 「これだけならできる」と思えるレベルまでハードルを下げるのがポイント。
- 「毎日掃除30分」→ 続かない。「毎日ゴミを1つ捨てる」→ 続く。
- 「床に落ちてるものを1つ拾う」「使ったものを元に戻す」など、小さな習慣を積み重ねる。
- 「全部片付けなきゃ」ではなく 「1つでも片付けばOK」の意識で続けると、結果的に部屋はきれいになる。
- 成功体験を積み重ねることが大事。「できた!」が増えると、自然ともっとやりたくなる。
最初から「完璧に片付けよう!」と思わなくてOKです。「今日はこれだけできた!」という小さな達成感を積み重ねることが、習慣化の近道。急がば回れです。
***
掃除・片付け習慣を続けるためには、無理をしすぎず、続けられる工夫をすることが大切。
ちょっとした意識の工夫で、習慣の投げ出しポイントを回避していきましょう。
まとめ
今回は、良い掃除・片付け習慣を身につけたい方に向けて、掃除・片付け習慣の必須要素や、続かない原因を克服する方法について解説し、習慣づくりに便利なアイテムや習慣中の注意点をご紹介しました。
- 良い掃除・片付け習慣は「分かりやすい手順」「時間の確保」「恩恵の実感」で形作られる。
- 良い掃除・片付け習慣は部屋の清潔度だけでなく、空間と心の余裕、時間とお金の節約にもつながる。
- 掃除・片付け習慣が続かない原因は「モチベーション・能力・きっかけ」のどれかが欠けているから。
- 「モチベーション・能力・きっかけ」を調整することで、良い掃除・片付け習慣を作れる。
- 無理をしすぎず、続けられる工夫を凝らすことが、習慣の投げ出しポイントを回避する上で重要。
掃除・片付けを習慣にすると、ただ部屋がキレイになるだけでなく、心の余裕や自己管理能力の向上など、さまざまな良い影響を受けることができます。
まずは、「1日5分だけ片付ける」「使ったものを元に戻す」など、簡単なルールを決めるところから始めてみましょう。 少しずつでも続けることが、習慣化の第一歩です。
掃除・片付け習慣を作っていく途中で、今やってることが合ってるのか迷ったときは、この記事の内容を何度も読み返して、続けやすく投げ出しづらい習慣に磨いていってください。良い掃除・片付け習慣を定着させ、部屋も心もスッキリとした暮らしを手に入れていきましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。