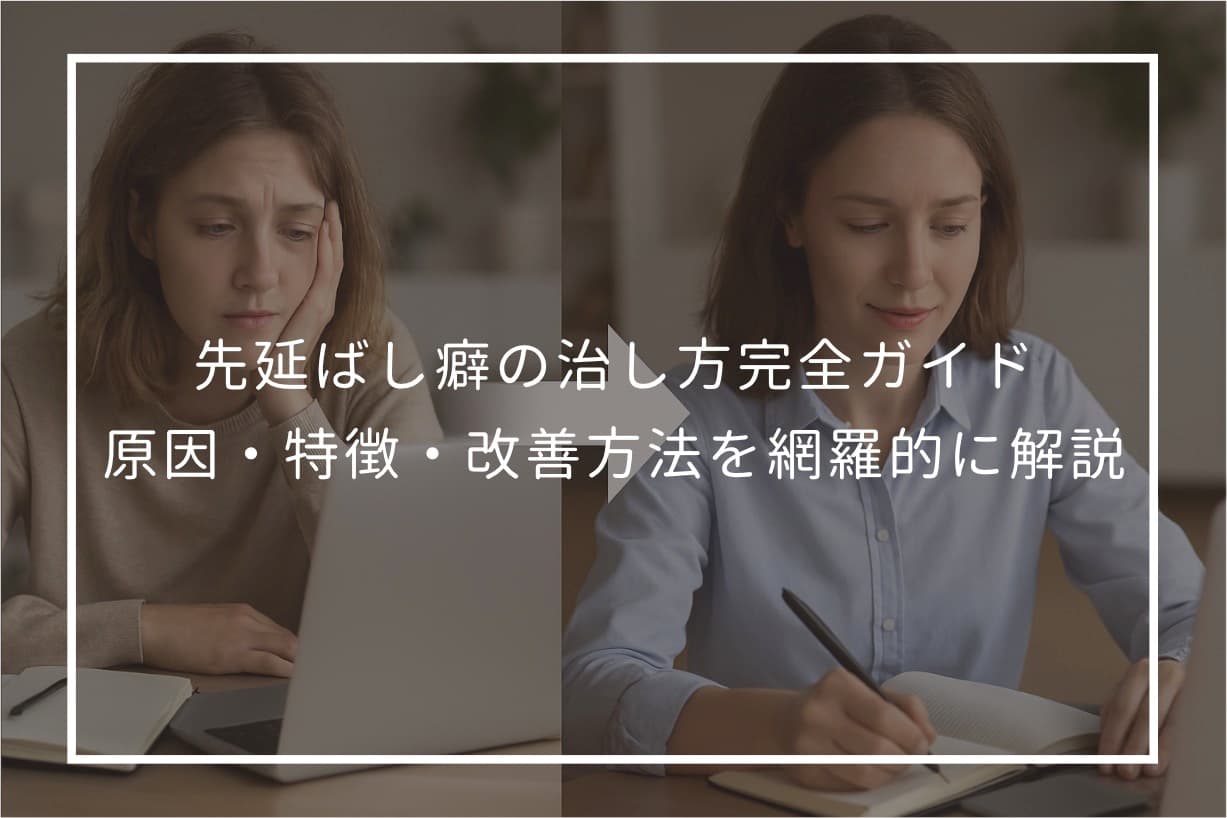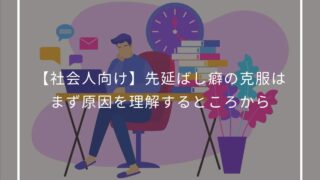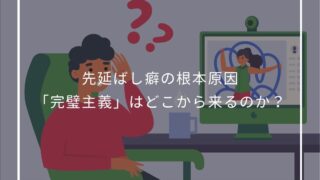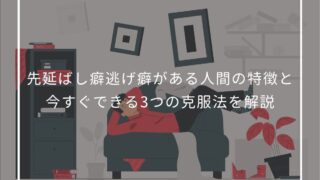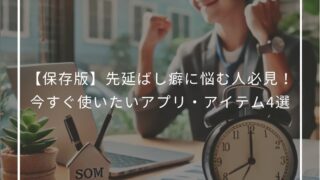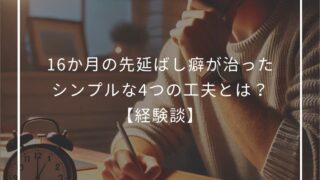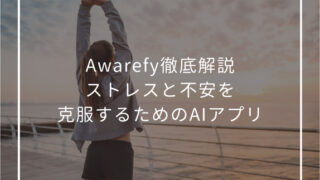けうzenです。
このページは「先延ばし癖」を治すために知るべきトピックを集約したガイド記事です。
手っ取り早く知りたい方のため、コンパクトにトピックを集約しています。
先延ばし癖がなかなか治らないという方には、タメなる記事になってるんじゃないかなと思います。
原因を理解せずに対処を考えるのは、雨漏りを止めずに濡れた床を拭き続けるようなものです。
このガイド記事を通して、自分の先延ばし癖に対する理解を深め、着実に解消していってください。
先延ばし癖の簡易自己診断テストもあるので、理解を深めるツールとして、ぜひご活用ください。
それでは、いってみましょう。
先延ばし癖とは
まず、先延ばし癖とは何か。
それは、「やるべきことを必要なタイミングで行えず、後回しにしてしまう癖のこと」を言います。
先延ばし癖が習慣化すると、仕事だけでなく、生活全般に悪い影響を及ぼしやすいです。
ちなみに、「合理的な延期」と「先延ばし」は別物です。
仕事上で、誰かの成果物がないと始められないタスクというのは良くあると思います。
営業であれば、スケジュール調整が合わなければ商談を延期するでしょう。
エンジニアであれば、要件定義が完了しなければ、技術選定もできません。
このような「個人の都合を超えた延期」は先延ばし癖ではありません。
今回は「個人の都合で生じる先延ばし」に焦点を当てて解説していきます。
合理的な延期とは違って、先延ばし癖は、「心理的な不安、外部環境の誘惑、モチベーションの問題から生じることが多いです。
後になってから「またできなかった…」と罪悪感や自己無力感を感じることが多い方は先延ばし癖が身についているのかもしれません。
そして先延ばし癖は、今一時を楽にするストレス対処の方法として根付いてしまうため、本人の意志だけで簡単に改善できるものではなかったりします。
先延ばし癖対処の判断基準
先延ばし癖は、実は誰にでもあるものです。どんな人でも多少先延ばしにしていることがあります。
ではそんな先延ばし癖は、どんな状態であれば早急な対処が必要なのか?
先延ばし癖対処の判断基準は以下の3つで測れます。
感情
先延ばしによって、常に「やらなかったこと」に対して後ろめたさや自己嫌悪を感じ、心の負担が大きくなるケースがあります。
例えば、週の半分以上で「またやるべきことができなかった…」というネガティブな感情があるなら、それは単なる一時的な失敗ではなく、心理的な負荷が蓄積している証拠です。
この場合、行動を起こす意欲自体も削がれ、さらに動き出せなくなる可能性があるため、対処する必要があります。
感情面における判断基準は、先延ばしによるネガティブ感情の頻度が「週の半分=週4日以上」かどうかです。
仕事
仕事における先延ばし癖は、個人の生産性や、現場全体に悪い影響を及ぼす可能性を持っています。
重要なタスク、特に締め切りの近いタスクを先延ばしにすると、成果物の質が悪くなったり、ミスやトラブルが増えるリスクがあります。
仕事上では、先延ばし癖によって、過去に重大なトラブルが3回以上起きてしまっている場合、対処が必要でしょう。早急な改善策を講じる必要があります。
日常生活
日常生活においても、先延ばし癖は大きな問題の種になり得ます。
例えば、家事や健康管理、プライベートの予定など、日常の基本的な活動を後回しにすると、生活の質そのものが低下する可能性があります。
予定のドタキャンやすっぽかしが増えると、家族や友人との関係にひびが入る場合もあります。
「今の日常環境を、変えれるはずなのに、変えれない自分が嫌になる」「先延ばしのせいで家族や友人との関係が悪くなっている」と感じる場合は、先延ばし癖への対処を考えた方が良いです。
先延ばし癖の簡易自己診断テスト
自分の先延ばし癖の深刻度を測る簡易的な尺度として、ここでは先延ばし癖の簡易自己診断テストを提供します。
この自己診断テストでは、日常生活や仕事、プライペートでの先延ばし癖の深刻度をYes/No形式で測ります。
自分自身の行動や感情に照らし合わせて、先延ばし癖の程度を把握する指標としてご活用ください。
質問
日常生活・仕事の影響に関する質問
1. 重要な締め切りがある仕事やタスクを、期限ギリギリまたは期限を過ぎてから取り組むことが多い。
2.「今やらなければならないこと」よりも、楽しいことや楽なことを優先してしまう傾向がある。
3. 期限が近づくと焦るものの、結局は行動に移せず後回しにしてしまう。
4.「明日やろう」と何度も先延ばしにし、結果としてタスクが溜まってしまっている。
5. 遅れを取り戻すために、徹夜や長時間作業を強いられることが頻発している。
感情・思考に関する質問
6. やるべきことを考えるだけで気持ちが重くなり、先延ばししたくなることが多い。
7.「完璧にやらなければ」と考えてしまって、始めるのが億劫になってしまう。
8. 自分を「怠け者」と感じて、自己否定に陥ることがしばしばある。
9. 自分の先延ばし行動が周囲に迷惑をかけていると感じることがある。
10. 先延ばしの結果、仕事や学業での成果が明らかに低下していると感じる。
行動パターンに関する質問
11. SNSや動画コンテンツ、ゲームなどに没頭し、本来のタスクを後回しにしてしまう。
12. やる気が出るのをただ待っているうちに、あっという間に時間が過ぎてしまう。
13. 計画を立てるものの、実際に実行するとき計画が全く役に立たないことが多い。
14. 以前に先延ばしの改善を試みたが、なかなか効果が出なかった経験がある。
15. 先延ばしが原因で、後になって大きなストレスや後悔を感じることがある。
判断基準
- Yesが4個以下:
- 先延ばしは支障のない範囲です。
自己管理に少し気をつけつつ過ごしていきましょう。
- 先延ばしは支障のない範囲です。
- Yesが5〜9個:
- 先延ばし癖が日常に支障をきたしている兆候があります。
原因を特定し、具体的な対処を考えましょう。
- 先延ばし癖が日常に支障をきたしている兆候があります。
- Yesが10個以上:
- 先延ばし癖が深刻な状態に達している可能性があります。
放置すると、仕事・学業・メンタルヘルスに悪影響を及ぼし続ける危険性あり。
専門家やカウンセラーへの相談をおすすめします。
- 先延ばし癖が深刻な状態に達している可能性があります。
先延ばし癖の原因
先延ばし癖の背景には、個人の心理状態や外部環境の複雑な影響が絡み合っています。
ここからは、先延ばし癖の主な原因を3つ解説していきます。
1つずつ見ていきます。
疲労
身体的な疲労や精神的な消耗は、先延ばしの大きな要因となります。これは当たり前ですね。
たとえば、十分な睡眠が取れていなかったり、長時間の作業が続いたりすると、脳はエネルギーを節約しようと働き、重いタスクを避けがちになります。
こうした疲労状態では、単純な作業であっても「今はいいや」と後回しにする選択が自然に出てきてしまいます。
曖昧さ
「始めるきっかけがない」「何から始めるか決まっていない」「タスクのゴールが不明確」「期限がない」など、先延ばしにはさまざまな曖昧さが関与しています。
タスクの内容や、そもそも何のためのタスクなのか、ゴールが明確でないと、どこから手を付ければ良いのか分かりません。
そして、曖昧さが積み重なると先延ばしが発生しやすくなるのです。
たとえば、「報告書作成」を考えてみましょう。
報告書を作る意味に多少疑問があったとしても、フォーマットがあって、期限もあるなら取り掛かり始めやすいでしょう。
目的は曖昧ですが、手順と期限の明確さがカバーして比較的着手しやすいです。
対して「ダイエット」の場合はどうでしょうか。
仕事ではないので全て自分で決めることになりますが、「何から始めればいいか分からない」「ゴールが決まってない」「期限もない」「きっかけもない」となると永久に先延ばししてしまいます。
目的がはっきりしていても、手順、期限、目標の曖昧さが足を引っ張って取りかかれない状態です。
曖昧さが積み重なれば積み重なるほど、今行動する難易度が高まり、先延ばしが発生しやすくなります。
外部環境
外部環境、特に興味を惹きつけるモノや気を散らす要因は、間接的に先延ばしを引き起こす要素になります。
現代は、スマホやインターネット、テレビなど、常に注意を引く媒体が身近にいくつも存在していて、興味を惹きつけられてしまいやすい環境が整っています。
楽しい、面白いコンテンツにすぐアクセスできる今の時代、すべきことに取り組む時間は簡単に奪われ、間接的に先延ばしは発生しやすい状況にあります。
他方、忙しすぎてやらなければならないことで手一杯、抱えているものが多すぎる場合も、緊急ではないこと(例えば、健康管理、人付き合い、旅行など)はどこまでも後回しになりやすいです。
このような環境要因は、自分自身の意志だけではコントロールが難しいため、環境整備の工夫が必要です。
先延ばし癖がある人の特徴
先延ばし癖が身についてしまった人には、いくつかの共通した特徴が見られます。
ここからは、先延ばし癖を持つ人に共通する代表的な特徴を紹介していきます。
完璧主義
完璧主義の人は、「完璧にできないなら、やらないほうがマシ」と最初の一歩を踏み出すのに大きな障壁を感じやすいです。
失敗を極度に恐れるため、少しでも不完全な状態になることを過度に避けようとします。
やるべきことに取りかかる前に、全てを見通そうと、準備や計画に時間を費やしてしまい、結果として実際の作業自体が先延ばしにされるケースが多いです。
しかし、正解のない問題が多い現代、事前にすべてを見通せることはほとんどありません。
「60点でいいから、とりあえず前に進める」と柔軟な心構えにシフトしていくことが必要でしょう。
短期的快楽優先
先延ばし癖がある人は、目の前の楽しさや一時的な快楽に流されやすい傾向があります。
長期的な成果よりも瞬間的な満足感を重視するため、重要なタスクが後回しにされがちです。
たとえば、仕事中にSNSや動画を見たり、家でやるべきことがあるのにゲームに没頭してしまうなど、今が楽しかったり楽な行動に興味を惹きつけられてしまいます。
目先の楽さを提供するコンテンツに飼い慣らされてしまうと、将来的な成果や目標達成のための積み重ねが難しくなります。
低い自己効力感
自己効力感とは、「自分にならできる」「難しいことでも少しずつこなしていく力が自分にはある」と感じる力のことです。
過去の失敗が原因で、自己効力感が低くなっている人は、新しいことに挑戦する前に「自分にはできない」と決めつけてしまいがちです。
自己効力感が低いと、新しいことであればどんな小さなタスクでも勇気が湧かず、結果として先延ばしに陥りやすくなります。
この場合、自己効力感を少しずつ高めていく小さな小さな目標設定と成功体験の積み重ねが必要です。
モチベーション主導
「やる気が出たら始める」という考えに依存していると、モチベーションが一時的に高まったときのみ行動に移し、気分が落ち込むとすぐに中断してしまうという特徴があります。
始めは意欲的に取り組むものの、途中でやる気の熱が冷めると、再びモチベーションが上がるまで待つという悪循環に陥るため、継続性に欠ける結果となります。
安定した行動パターンを作るためには、感情に左右されない仕組み作りが不可欠です。
先延ばし癖を治す具体的な工夫
先延ばし癖は、日常の行動や環境で少しずつ紐が絡まっていくように身についていきます。
ということは、行動と環境に工夫を加えることで、絡まった紐を解いていくように、少しずつ治していくこともできるということです。
ここからは、絡まった紐の解き方、つまり先延ばし癖を治すための具体的な工夫を紹介していきます。
きっかけ設置
まず、自分がタスクを始めるための明確な「きっかけ」を設定することが大切です。
たとえば、スマホやPCのアラームで自分に時間が来たことを気づかせます。
そして、特定の動作(コーヒーを淹れて席に着く、軽く伸びをするなど)をタスク開始のトリガーにします。
脳に「そろそろ作業を始めるサインだな」と気づかせる仕組みを作るのです。
アラームが鳴って時間が来たことに気付いたら、トリガー動作をする。トリガー動作をしたらタスクに取り掛かる。
明確な「きっかけ」を設置して、ルーティンとして毎日繰り返していきます。
すると、朝起きたら歯を磨くのと同じように、意識せずとも自動的にこなせる習慣になっていきます。
きっかけ設置は、先延ばし癖を自然と減らす第一段階として有用です。
始めの一歩作成
トリガー動作でやるべきことに意識を向けられたら、次は「始めの一歩」を作りましょう。
やるべきことに取り掛かる始めの一歩を、極限までシンプルかつ具体的なものします。
例えば、「ノートPCを開く」「作業に必要なアプリ画面を開く」など、大体5秒以内にできる具体的なことを一番始めの手順として決めましょう。
始めること自体が容易になり、実際に作業を開始するとそのまま続けやすい状況が生まれます。
小さな一歩から徐々にタスクに入り込んでいき、止まっていた水車が少しの水で回り始めるように、動き出しやすくなります。
「始めの一歩」を作って、タスクに入り込む心理的なハードル下げていきましょう。
環境整備
先延ばし回避のためには、物理的な環境を整えることも不可欠です。
作業に集中できる静かなスペースを確保する、作業中は誘惑(スマホやPCの特定のアプリなど)を遠ざけること。
自分の先延ばしを誘発する物理的な環境要因を整えると、自然と今しようとしていることに没頭する状況を作り出しやすくなります。
もう1つの工夫は、作業だけをする場所を作ること。
例えば、自室のデスクを「ここは作業するための場所だ」と、場所とその場所ですることを紐づけることで、行動のトリガーにすることも効果的です。
もちろん、誘惑を遠ざけて没頭しやすい場所に仕立てる必要はありますが。
日常的に自分の取りたい行動を促す工夫を凝らして、今すべきことに自然と取りかかれる環境を作り上げていきましょう。
よくある質問
- Qすぐやる気がなくなってしまうのですが、どうすれば継続できますか?
- A
やる気がなくなって継続できないという方には、「いつも通り」を1日のどこかで作ることをおすすめします。
たとえば、タスクに取り組む前に「マインドフルネス」を取り入れると、一時的な感情をニュートラルに戻すことができます。
「マインドフルネス」は、独学で0から習得するのは難しいですが、アプリ「Awarefy」を使えば、お家ですぐに実践することができます。
「いつも通り」を作るルーティンを取り入れ、無意識に作業に取り掛かれる、取り掛かりたくなる仕組みを構築していきましょう。
- Q先延ばしのせいで自己嫌悪に陥ります。どうすれば自信を持てますか?
- A
ネガティブな感情とうまくやっていくためには、まずは小さな成功体験を意識的に積み重ね、自分を認めてあげる習慣を取り入れることが大切です。
「今日は5分だけ作業できた」や「計画を立てることができた」といった小さな達成を記録してみましょう。
出来事や考えをその時の感情と共に記録していく「コラム法」という記録方法があります。コラム法を使うことで、自分の感情を観察して寄り添いつつ、小さな達成を記録していくことができます。
ちなみにコラム法は、アプリ「Awarefy」で実践することができます。
- QついSNSやYouTubeを見てしまい、やるべきことを後回しにしてしまいます。どうすればやめられますか?
- A
やるべきことをする時間が来たことを自分に気づかせる工夫をしましょう。
スマホやPCにアラームを設置して時間が来たことに気づくタイミングを作りましょう。まずは気づくところからです。
作業中にSNSやYouTubeに気を散らされる場合は、デジタル的・物理的に誘惑を遠ざける工夫が必要です。
誘惑を遠ざけるには、タイムロッキングコンテナを使うことをおすすめします。
スマホなどをコンテナに入れて指定した時間中物理的に封印することができます。デジタル的・物理的な工夫を加えて、誘惑を遠ざけていきましょう。
- Q先延ばしの原因が分かりません。どうやって見つければいいですか?
- A
先延ばしの原因は人それぞれ異なるため、自分自身の行動パターンや感情の変化を客観的に観察することが重要です。
具体的には、「何が原因で行動を開始できなかったのか」、「どのような状況で先延ばししやすいか」を言葉にできれば、改善策のヒントを得られる可能性があります。
また、自分の先延ばし癖を根本原因から深く理解して、その対策を習得したい方は、Udemyの先延ばし対策専門講座をおすすめします。
Error費用はかなり高めですが、これからの人生分、先延ばし癖とうまくやっていく指針が手に入ると考えれば、価値ありです。
まとめ
今回は、先延ばし癖に悩む方に向けて、その原因・特徴・具体的な改善方法について網羅的に解説しました。
- 先延ばし癖とは、やるべきことを意識的・無意識的に後回しにしてしまう習慣で、心理的負担や生活・仕事に悪影響を及ぼす。
- 先延ばし癖に対処が必要な判断基準は、「感情」「仕事」「日常生活」の3つへの支障度で測る。
- 先延ばし癖の原因は「疲労」「曖昧さ」「外部環境」などが複雑に絡み合っている。
- 先延ばし癖がある人のよくある特徴は「完璧主義」「短期的快楽優先」「低い自己効力感」「モチベーション依存」。
- 先延ばし癖解消のための工夫は「きっかけ作り」「始めの一歩作成」「環境整備」。
先延ばし癖解消への道は、小さな一歩を踏み出すことで始まります。
ぜひ、自分に合った対策を取り入れ、先延ばし癖を克服する第一歩を踏み出してください。
本記事で紹介した内容があなたの先延ばし癖改善の一助となれば嬉々無上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。