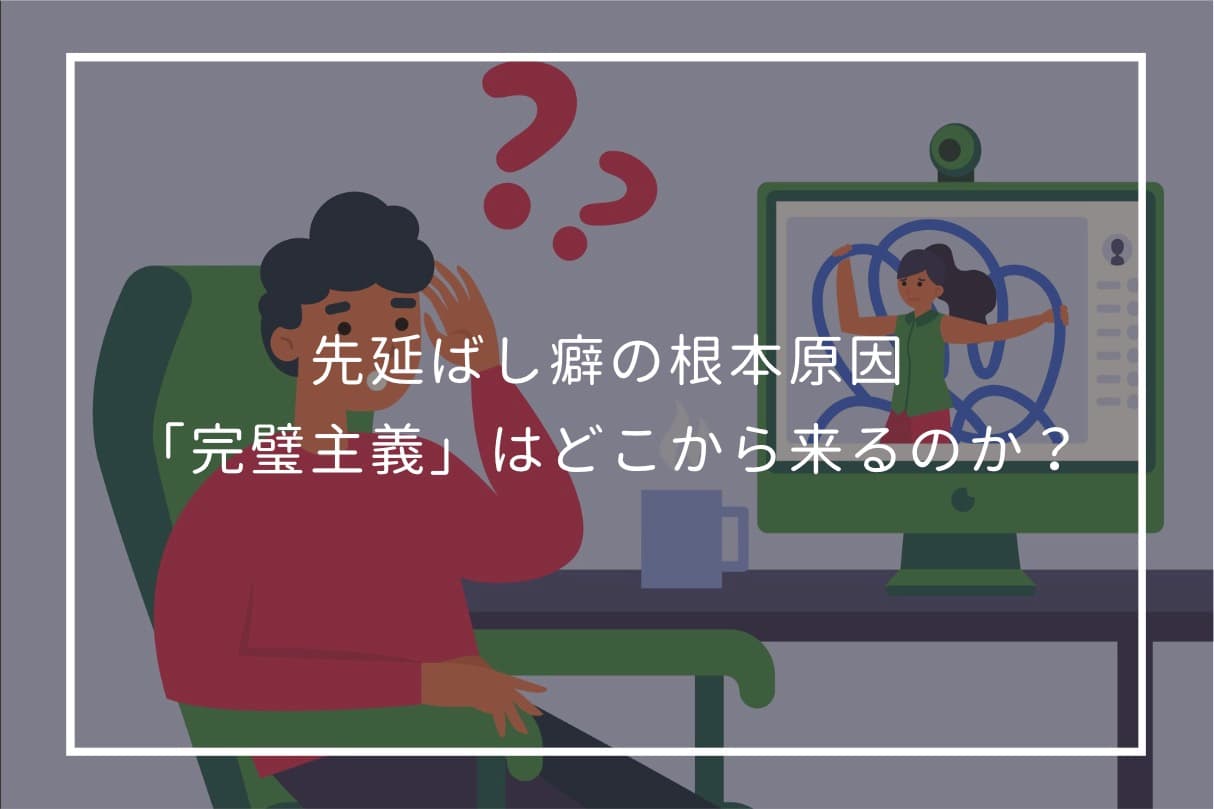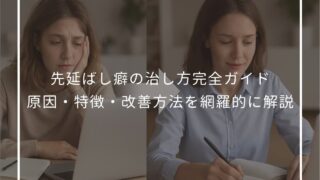あなたの先延ばしはどこから?
ある研究によると、先延ばし癖には、2種類あると言われています。
- 「覚醒型先延ばし」:ギリギリになってからでないとやる気が出ない。
- 「回避型先延ばし」:失敗するくらいならやらない方がマシ。
中でも「回避型先延ばし」は、完璧主義と関係しています。
あなたは、何か大切なことに取り組もうとすると、いつも完璧を求めるあまりつい手が出せなくなってしまうことはないでしょうか。
- ちょっとしたミスでも、自分の価値が無くなってしまうように感じる。
- 完璧な結果を求めるあまり、行動に踏み出せず締切ぎりぎりになってしまう。
- 自己批判心が強く、どんなに他者から評価されても自信が持てない。
行動に踏み出せない状態が続くと、仕事の質が落ちたり、周囲との信頼関係が損なわれる危険性もあります。
もしこの現状を放置すると、次第に「行動できない → 自己嫌悪 → 行動できない → …」と悪循環に陥り、抜け出せなくなってしまうかもしれません。
言うまでもなく、この記事に辿り着いた今が、先延ばし癖を治す無二のタイミングです。
では、そもそも先延ばし癖の根本原因である「完璧主義」はどこから来るのでしょうか。
この記事では、なぜ完璧主義が私たちに根付くのか、そしてその完璧主義がどのように先延ばし癖を引き起こすのか、解説していきます。
また、完璧主義を手放し、前に進むための具体的な方法もご紹介します。
この記事を読むことで、あなたの完璧主義がどこから来ているのか、完璧主義がどのように先延ばしの原因となっているのかを理解し、具体的な対策を学ぶことができます。
完璧主義が身についた原因を知り、その上で着実に完璧主義を手放していきたい方は、ぜひ最後までお読みください。
完璧主義が生まれる理由
完璧主義は、単なる個人の性格や気質の話で終わるものではなく、幼少期の経験や社会・文化など、複数の要因が絡み合って形成されていきます。
まずは、なぜ私たちは完璧を求めすぎてしまうのか、以下の3つの視点から、その根本原因に迫っていきます。
1つずつ見ていきます。
家庭環境
完璧主義は、幼少期の家庭環境に大きく影響を受けると言われています。
親からの期待や過度な干渉は、子どもだった頃の私たちに「完璧でなければ価値がない」というメッセージを無意識に刷り込みます。
たとえば、テストで90点を取っても「なぜ100点じゃないの?」と言われた経験があれば、常に「満点を目指さねば」と感じるようになるかもしれません。
成績や結果など、外面的な成果のみを重視された経験は「失敗=無価値」という思い込みを強めます。
兄弟・姉妹間や他者との比較も影響します。
「お兄ちゃん・お姉ちゃんはできたのに」などと言われ続けると、「自分は完璧でなければ認められない」という価値観が出来上がります。
このような環境で育った人は、大人になっても「ミスをしてはいけない」「成果がすべて」と考えがちになり、完璧主義の基盤が形成されるのです。
社会的・文化的背景
日本社会には、失敗を過度に恐れる文化が根付いています。
学校や職場など、日常的に「完璧であること」が暗黙の了解となりやすい環境が存在しています。
さらに、日本特有の同調圧力も完璧主義を後押ししています。
「忖度」「空気を読む」などの社会的価値観が根強く、他者からの評価や比較に敏感になりやすくなります。
加えて、SNSの普及により、常に他者の成功体験や成果を目にする機会が増え、「もっと完璧にやらなければ」という焦りを感じる人も少なくありません。
このような社会環境が、完璧主義を内面化しやすくする大きな要因になっています。
時間志向
完璧主義には、時間志向が関係していると言われています。
具体的には「過去否定志向」が関係している場合があります。
「過去否定志向」とは、過去の失敗やミスに対して、痛み、トラウマ、後悔など否定的な捉え方をしている状態のことです。
未来に対する希望や前向きな期待よりも、「過去の失敗を繰り返したくない」という気持ちが強く、「次こそ完璧でないといけない」という考えが強まります。
過去の経験が重くのしかかり、「行動するより、失敗しないこと」が優先される思考パターンに陥りやすいのです。
この時間志向の歪みが、完璧主義を生み出す心理的要因のひとつとなります。
完璧主義と先延ばし癖の関係
完璧主義は、先延ばし癖の根本に深く関係しています。
完璧を求めるあまり、不安や恐怖から行動を避けてしまうメカニズムが隠れているのです。
ここでは、完璧主義がどのようにして先延ばし癖を引き起こしてしまうのか、具体的な心理状態や行動パターンを詳しく見ていきます。
失敗への恐怖と自己防衛
完璧主義者は、「失敗=自分の価値が無くなる」という極端な思考に陥りやすくなっています。
少しのミスでも自身の価値が大きく失われることを過剰に恐れる傾向にあります。
そのため、失敗そのものだけでなく「失敗するかもしれない状況」に対しても強い不安やストレスを感じます。
この不安から身を守る手段として、無意識に「行動しない」という回避行動、つまり先延ばしを選ぶのです。
実際に手を付けなければ、失敗は起こりません。
また、締切直前まで着手しないことで「時間がなかったから仕方ない」と自分に言い訳を用意することもできます。
これは、自分の価値が下がることを避けるための自己防衛反応としての先延ばしと言えます。
過度な自己批判
完璧主義の人は、自分に対して非常に厳しい評価を下しがちです。
たとえ他者から評価されていても「自分はダメだ」「能力がない」と強く自己批判する傾向があります。
良く言えば「謙虚」ですが、このような過度な自己批判は安らぐ瞬間がありません。
出来事を絶えず悲観することは耐え難く、行動そのものが億劫になっていきます。
結果、「どうやってもダメだ」という自己無力感に行き着き、「それなら初めから行動しなければいい」と先延ばししてしまうことになります。
分析麻痺
完璧主義者は「確実に成功する方法」を求め、過剰に情報を集めたり、完璧な計画を練ろうとする傾向があります。
しかし、その過程で「パラドックス・オブ・チョイス」と呼ばれる現象が発生しやすくなります。
選択肢が多すぎることで、かえって決断できなくなる状態です。
リスクを最小化しようと考えすぎてしまい、「これでは不十分かもしれない」「もっと準備が必要だ」と考えるうちに、行動を起こせなくなることも少なくありません。
結果として、準備や検討ばかりに時間を費やし、実際の行動には移れない「分析麻痺」に陥るのです。
考えすぎて動けない状態が続くと、自己嫌悪や焦燥感が強まり、さらに行動から遠ざかるという負のスパイラルを引き起こします。
完璧主義が引き起こす先延ばしの問題
完璧主義が引き起こす先延ばしには、単なる遅延だけでは済まされない悪影響があります。
ここからは、完璧主義が原因で生じる先延ばしは、どのような問題を生むのかを具体的に解説します。
仕事の質低下
完璧主義による先延ばしは、仕事の質を大きく損ないます。
着手が遅れるので、締切直前に追い込まれる状況を自ら作り出してしまいます。
計画や準備が不十分なまま作業を進めざるを得なくなり、満足のいくアウトプットが出せない結果になりやすいです。
また、十分な時間がないことで、他者からの助言やフィードバックを取り込む余裕も失われます。
そのため、視野が狭くなり独善的なアウトプットになりがちです。
自己嫌悪
やるべきことに取り組めない状況が続くと、次第に「またできなかった」「また同じことを繰り返している」と自己嫌悪の念が湧いてきます。
さらに、「行動しない自分」に対する罪悪感から、ますます行動が重くなり、やる気が出なくなるという悪循環が強まります。
モチベーション低下→先延ばし→自己嫌悪→モチベーション低下 → …という負の連鎖を断ち切るのが難しくなり、落ち込みやすく、強い不安を感じやすくなるでしょう。
周囲との関係性悪化
先延ばしが招く問題は、自分自身だけでなく、周囲との関係性にも影響を及ぼします。
作業の遅延から、チームメンバーや関係者からの信頼が下がりやすくなります。
「迷惑をかけてしまった」という焦りから、「今度こそ完璧にやらねば」というプレッシャーを自分に課し、さらに状況を悪化させることも。
また、期限ギリギリでのやり取りが増えることで、相手とのコミュニケーションが雑になり、関係性がぎくしゃくしやすくなります。
さらに、タスクを抱え込みやすくなるため、他人に相談したり助けを求めるタイミングを逃し、孤立を深めるケースもあります。
完璧主義を手放す方法
ここまで、完璧主義と先延ばし癖の関係、そして完璧主義の引き起こす問題を解説してきました。
では、完璧を求めすぎる思考を少しずつ緩め、先延ばし癖から解き放たれるためには、どんな考え方や行動を取り入れれば良いのでしょうか?
ここからは「どうすれば完璧主義を手放せるのか」具体的な方法について解説していきます。
前進主義への転換
「失敗できない」という考えから「まずは進めることが大事」という前進主義へのシフトが、完璧主義を手放す第一歩です。
完璧さよりも「とりあえず触ってみる」ことに価値を置くマインドを育てていきましょう。
まずは「60〜80%の完成度でもOK」と自分に許可を出すことが大切です。
とりあえず始めれば、始める前までは見えてなかったものが見えてきます。
終わりが見えず始められなかったものが、案外近くにゴールがあったり、難しそうと躊躇してたものが、初めて見たら案外簡単にできたりします。
人は誰しも、未知のものには実際以上に恐怖や不安を感じるもの。
ちょっとだけ触って、未知のものが少し既知になったら、不安がわずかに和らいだことに気づくはずです。
小さなジャブを積み重ねていけば、「ここまでは前に来た」と既知の経験が増えて、とりあえず始めるハードルが下がっていきます。
「やればできる」という成功体験が2回3回と集まっていけば、過度な完璧主義から少しずつ離れていく自分に気がつくかもしれません。
タスクのチャンクダウン
タスクが大きすぎると、完璧を目指すあまり「手を付けられない」という状況に陥りやすくなります。
そこで有効なのが、「チャンクダウン」です。
「チャンクダウン」とは、大きなタスクを小さなタスクに細分化すること。
大きなタスクを、具体的で実行しやすい小さなタスクに分けることで、心理的な負担感を軽減できます。
そして「始めの一歩」を明確にすることで、行動に取り掛かり始めやすくなります。
たとえば「プレゼン資料を作る」という大きな目標があれば、「資料の構成を考える」「必要なデータを集める」「スライド1枚目を作る」といったように細かく分けて考えます。
細かく分けて進めることで、今やることが明確に認識できるようになり、「何をすればいいか分からない → 先延ばし」のパターンを減らせます。
大きすぎるタスクの、小さくて明確なタスクへのチャンクダウンが、先延ばしを防ぐ強力な武器となります。
リフレーミング
完璧主義には「0か100」の極端な思考や、「ミス・失敗=自分の価値が無くなる」という思い込みが根底にあります。
これを柔軟に捉え直すために効果的なのが「リフレーミング」です。
たとえば「完璧じゃない自分には価値がない」という考え方を「60%でも十分価値がある」「一旦未完成でも改善できる」という風に言い換える練習をします。
失敗を「悪いもの」と断定せず、「成功への階段を1段登った」と捉え方を変えることで、心理的なハードルは大きく下がります。
日常の中で気づいたネガティブな思考パターンに対して、意識的に別の視点を考えてみましょう。
異なる視点を持つ癖をつけると、物事を柔軟に捉えられるようになり、自然と行動しやすくなっていきます。
まとめ
今回は、先延ばし癖の根本原因である完璧主義はどこからくるのか、完璧主義が生まれる理由、完璧主義と先延ばしの関係について解説し、完璧主義を手放す方法をご紹介しました。
- 完璧主義は幼少期の家庭環境や社会・文化の影響を強く受け、過去否定から来る失敗への恐怖や過度な自己批判が先延ばしを引き起こす。
- 完璧主義は、仕事の質に悪影響となる可能性が高く、他者からの信頼だけでなく自分自身への信頼にも大きく傷をつける。
- 完璧主義を手放し、先延ばし癖を解消するためには、「前進主義」「チャンクダウン」「リフレーミング」など、マインドの転換や工夫が必要。
完璧主義は、今まで自分が置かれてきた環境・関わった人の影響を受けて少しずつあなたの中に作り上げられていった価値観です。
この価値観を手放すときもまた、少しずつ解いていくしかないところがまた厄介に感じることでしょう。
しかし、あなたは必ず完璧主義を手放すことができます。
なぜなら、あなたは完璧主義を手放そうとこの記事を見つけ、ここまで読み進められてきたからです。
より良い自分になるための方法を調べる行動に乗り出せていることにあなたはお気づきでしょう。
あなたならきっと、完璧主義を手放し、先延ばし癖を克服できます。
まずは小さな行動から始めてみましょう。
完璧を目指さなくても、「まずは始める」「60%でOK」と自分を許してみてください。
そして、大きなことを小さく切り分けて取り組み、少しずつ進んでいってください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。